2025年11月
ASD(自閉スペクトラム症)の“ソーシャル・カモフラージュ” 11月16日
ASD(自閉スペクトラム症)の“ソーシャル・カモフラージュ”について詳しく分析した論文を読みました。内容があまりにも、私が日々の診療で感じてきた患者さんの姿と一致しており、「まさにこれだ」と腑に落ちる思いがありました。
まず、ソーシャル・カモフラージュとは、ASDの人が周囲から“普通”に見えるように自分を調整し、努力して振る舞う行動のことです。もちろん誰もが、社会では程度の差こそあれ「社会的ペルソナ」を使い分けています。職場で丁寧に話したり、初対面では慎重に振る舞ったりする、あの“社会用の顔”です。しかしASDの人の場合は、そのレベルが桁違いです。相槌やアイコンタクト、声の抑揚、表情の作り方、といった細かなコミュニケーション要素を、まるで外国語の文法を確認するように“頭で考えながら”実行しているのです。
論文ではカモフラージュを「補償」「マスキング」「同化」の3つに分類していました。あらかじめ会話の台本を準備したり、本当は苦手な視線合わせを頑張ったり、周囲の仕草をコピーして場に溶け込もうとするなど、その内容は非常に繊細かつ高度なものです。
特に印象深かったのが、ASDの女性が診断されにくい理由についての説明でした。女性は小さい頃から「周囲に合わせる」「空気を読む」といった社会的期待を受けやすく、そのためカモフラージュがより自然に、そして効果的に働きやすいという指摘です。興味の対象も、アイドルやキャラクターなど周囲と同じように見えるものに向かうことがあり、外からは特性が見えにくくなります。
この点は、私の外来でもたびたび見られる特徴です。学校の先生からは「問題なくやれています」「しっかりしています」と評価されているのに、家に帰るとぐったり疲れて動けなくなる。家族にだけ強い癇癪や八つ当たりを見せる──そうした相談は決して珍しくありません。「学校では頑張っているのに、なぜ家では…?」と親御さんが戸惑う背景に、このカモフラージュが潜んでいることが多いのです。
論文ではさらに興味深い実験結果が示されていました。初対面の会話の“最初の10秒間・音声なしの映像”だけを別の人に見せて評価してもらうというもので、ASDの人は全体として第一印象が低く、とくにASDの男性は男性評価者から厳しい評価を受けやすい傾向がありました。社会的に求められる「男らしさ」の規範が影響しているのではないか、という指摘もあります。逆に、第一印象が良い人ほど診断が遅れるという関連も示されていました。
これも、臨床での実感と重なります。明るく受け答えができるため「特に問題ありません」と学校で言われてきた子が、家では疲労困憊し、限界まで無理をしているケースは少なくありません。第一印象の良さが、むしろ支援の機会を遠ざけてしまうのです。
こうした文献を読むたびに、私たちが数秒で抱く印象がどれほど大きな意味を持ちうるか、あらためて考えさせられます。「見た目が普通だから大丈夫」という思い込みは、当事者が抱える“見えない努力と疲労”を覆い隠してしまいます。
カモフラージュは、ASDの人にとって社会で生き抜くためのサバイバル戦略です。しかし、それは同時に心身を大きくすり減らす行為でもあります。文献が示していた知見は、私がこれまで臨床で感じてきた事実を科学的に裏付けてくれるものであり、より多くの子どもや大人が「ありのまま」でいられる環境を整える必要性を、強く感じさせてくれました。
Belcher HL. Et al.Camouflaging Intent, First Impressions, and Age of ASC Diagnosis in Autistic Men and Women. J Autism Dev Disord. 2022 Aug;52(8):3413-3426
2025年10月
ノーベル賞の光と影:日本の科学研究が直面する「未来への危機」 10月26日
2025年、日本人研究者が2人もノーベル賞を受賞しました。制御性T細胞を発見した坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を、極小の穴が無数に開いた「金属有機構造体(MOF)」を開発した北川進氏がノーベル化学賞を受賞。お二人とも京都大学出身で、少しだけ京大に在籍していた私としては、まるで母校の快挙のようにうれしく感じます。
坂口氏の研究は自己免疫疾患の理解や治療に道を開き、北川氏のMOFは環境・エネルギー分野に革命を起こす可能性を秘めています。まさに世界に誇る成果です。
しかしその一方で、日本の科学研究全体を見渡すと、決して楽観できない状況にあります。長期的に見ると「注目度の高い論文(Top10%補正論文数)」の国際シェアが一貫して低下しており、日本は世界13位にまで後退しました。かつては3位だったことを思うと、その落差は大きい。今では韓国、スペイン、イランなどの後塵を拝しているのが現実です。
背景にはいくつかの構造的問題があります。まず、基礎研究を支える基盤の弱体化。大学や研究機関の運営費交付金が年々減少し、長期的・挑戦的な研究が難しくなっています。さらに、短期的な成果を求める風潮が強まり、「すぐに役立つ研究」ばかりが評価される傾向があります。しかし、ノーベル賞級の発見は往々にして、すぐには成果が見えない地道な基礎研究の積み重ねから生まれるものです。
加えて、若手研究者のキャリアの不安定化も深刻です。ポストが限られ、任期付きの職ばかりが増え、安定して研究を続ける環境が整っていません。その結果、研究時間が減り、優秀な人材が企業や海外に流出しています。さらに、国際的な連携や新興領域への参画の遅れも指摘されています。世界の研究は急速に広がるAIや量子技術、生命科学の新潮流へと動いていますが、日本はその波に十分に乗り切れていません。
科学技術研究は、日本の未来を支える基盤です。人口減少や資源の乏しさを補うには、知恵と技術の力が欠かせません。新しい医療、エネルギー、AIなどの研究は、国民の生活を豊かにし、地球規模の課題解決にもつながります。科学技術への投資は「費用」ではなく「未来への投資」です。
近年、政治の側でも希望の兆しはあります。高市首相は所信表明演説で「新技術立国」を目指すと明言しました。言葉だけでなく、実際の予算や制度にどれだけ反映されるかが鍵となります。短期的な成果を追うのではなく、10年、20年先を見据えた長期的な視点での支援が不可欠です。
坂口氏や北川氏の受賞は、「日本の科学はまだ世界に通用する力を持っている」という証でもあります。その灯を消さないために、社会全体で研究を支える意識を取り戻すことが必要です。研究者が安心して挑戦できる環境を整え、子どもたちが「科学者になりたい」と夢を語れる国であり続けたい――。今回の二つのノーベル賞は、そのための大切なメッセージを私たちに投げかけています。

2025年9月
ロボットの反逆 ヒトは生存機械にすぎないのか 9月19日
私たちは、日々、「自分自身の意思」で生きていると感じています。しかし、果たして本当にそういえるのでしょうか?
リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』の思想を継承する認知科学者、キース・E・スタノヴィッチは、著書『ロボットの反逆 ヒトは生存機械(サバイバルマシン)にすぎないのか』(ダイヤモンド社 2025)の中で、この根源的な問いに衝撃的な答えを提示します。彼は、人間を遺伝子とミームによってプログラムされた「ロボット」と見なし、そのプログラムに自覚的に反逆することこそが、現代における人生の意味だと説くのです。
なぜ人間は「ロボット」なのか?
スタノヴィッチが人間をロボットと見なす理由は、彼の二重過程理論(Dual-process theory)に集約されます。私たちの思考は、二つの異なるシステムによって動かされています。
一つは、直感的で迅速なシステム1です。これは、進化の過程で、生存と繁殖という目的のために遺伝子によってプログラムされた、無意識的な思考システムです。私たちが危険を察知して瞬時に逃げたり、他者との関係を直感的に判断したりするのは、このシステム1の働きによるものです。その思考は、認知バイアスと呼ばれる「思考の偏り」を多く含んでいます。
もう一つは、ミームという文化的なプログラムです。ミームは、情報単位として人から人へと伝播し、私たちの信念や行動を形作ります。スタノヴィッチは、宗教、道徳観、流行、あるいは「お金持ちが幸せ」といった価値観まで、すべてをミームと見なします。これらは、私たちの脳というハードウェア上で動くソフトウェアであり、私たちが意識しないうちに、思考を支配しています。
このように、私たちは遺伝子(ハードウェア)とミーム(ソフトウェア)という、二つの外部プログラムによって突き動かされているため、スタノヴィッチは私たちを「ロボット」と表現するのです。
「万能酸」としての進化論とノイラート的アプローチ
この厳しい現実を直視するため、スタノヴィッチは哲学者のダニエル・デネットが進化論を形容した言葉である「万能酸(universal acid)」という比喩を引用します。進化論は、従来の宗教的・神秘的な説明を「溶かし」、人間の行動や心の働きを科学的に解明する力を持っています。この「万能酸」は、私たちが持つ非合理性や、人生を物語として捉える傾向が、神の意志などではなく、遺伝子の利己的な複製戦略やミームの伝播といった自然現象にすぎないことを明らかにします。
そして、この真実を受け入れた上で、いかにしてプログラムを書き換えるか。スタノヴィッチは、「ノイラート的アプローチ」を提唱します。これは、哲学者オットー・ノイラートの「航海中の船の再建」という比喩に基づいています。私たちは、人生という航海中に、自分の信念という船を港に引き上げて、すべてを最初から作り直すことはできません。代わりに、航海を続けながら、一つずつ板(信念)を取り替え、少しずつ修理していくしかないのです。この漸進的なアプローチこそが、スタノヴィッチが提唱する「ロボットの反逆」の方法論です。
「ロボットの反逆」の方法
では、具体的にどうすれば「反逆」を起こせるのでしょうか? スタノヴィッチは、二つのステップを示唆します。
メタ認知による自己の客観視
反逆の第一歩は、自分が「ロボット」であることを自覚することです。これは、メタ認知と呼ばれる能力、つまり「自分の思考について考えること」を意味します。自分の感情や直感がなぜそのように動くのか、なぜ特定のミームを信じているのかを客観的に観察することで、私たちはシステム1の自動的な影響に気づくことができます。
合理性の追求と「良いミーム」のインストール
次に、システム2を意識的に使い、合理性を追求します。この合理性は、単に論理的な思考に留まりません。それは、「脱文脈的思考」とも呼ばれ、特定の感情や社会の慣習から離れ、普遍的な論理やデータに基づいて物事を考える能力を指します。
このプロセスを助けるのが、「良いミーム」のインストールです。例えば、ベイズ推定のような確率的思考や、科学的方法論、批判的思考といったミームは、私たちの脳をより合理的に機能させるための「良いプログラム」です。これを繰り返し実践することで、システム2の思考が習慣化され、エネルギー効率の良い思考パターンとしてシステム1に組み込まれていきます。
スタノヴィッチが提唱する「ロボットの反逆」の物語は、理性的には非常に納得がいくものです。遺伝子やミームのプログラムから自由になり、自律的に人生を設計するという考えは、現代を生きる私たちにとって、極めて魅力的な響きを持っています。
しかし、その道のりが平坦でないこともまた事実です。私たちが日々向き合うのは、無意識のうちに働くシステム1の圧倒的な力です。感情的な衝動、思考の怠け癖、社会的な圧力……。これらに常に抗い、意識的にシステム2を駆使し続けることは、並大抵の意志力では成し得ません。正直なところ、私自身も含め、多くの人にとって、この絶え間ない合理性の追求は、とても難しく、厳しい挑戦だと感じずにはいられません。
それでも、スタノヴィッチが示した道は、私たちに一つの希望を与えてくれます。それは、完璧なロボットの反逆者になることではなく、その困難なプロセスそのものに価値があるということです。私たちは、たとえ不完全であっても、自らの思考と向き合い、少しずつでもより良い自分へと変わっていくことができる。このささやかな努力の積み重ねこそが、私たちの人生に意味と目的を与えてくれるのかもしれません。
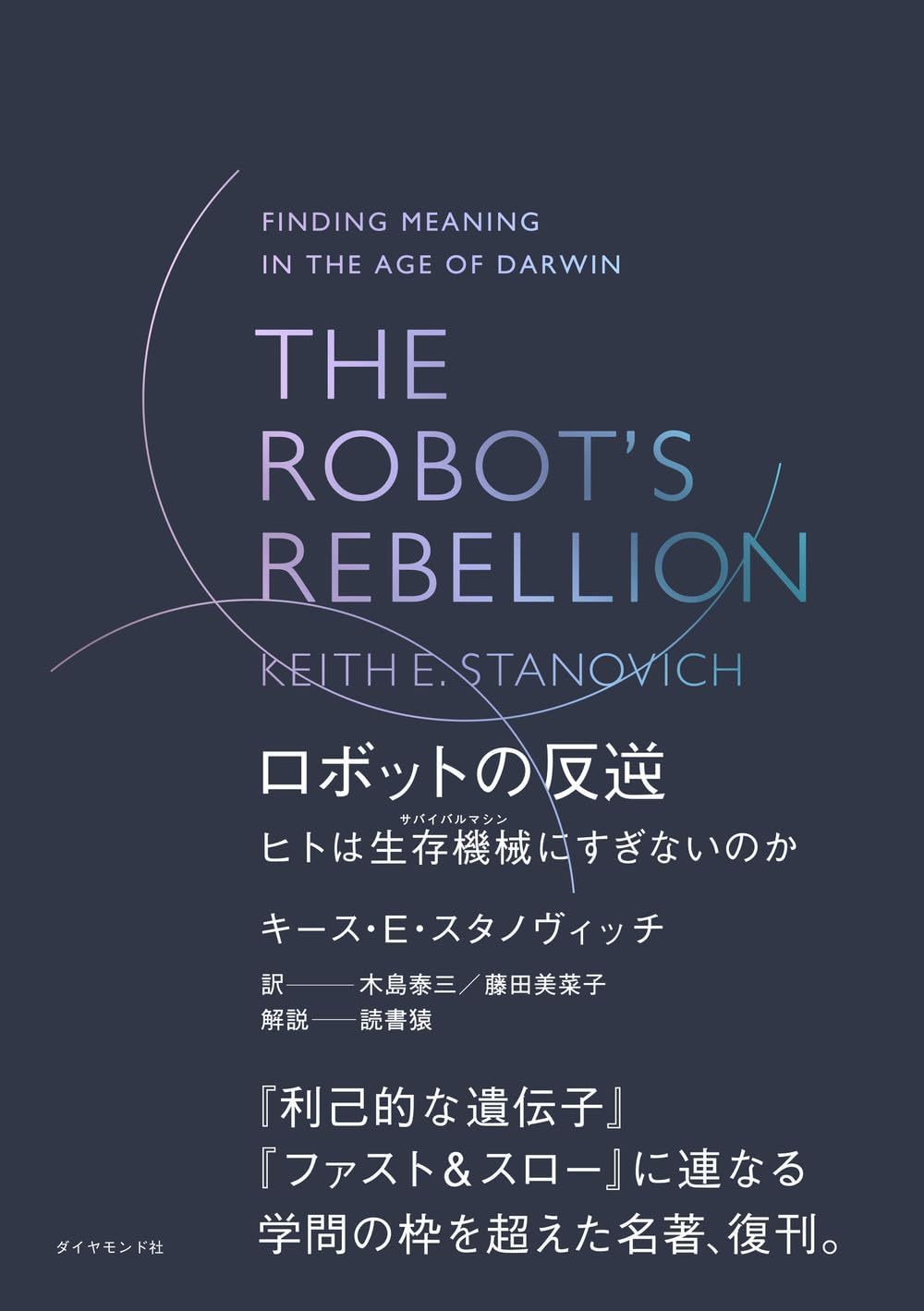
2025年8月
学校の存在感が揺らぐ時代に ―『学校がウソくさい』を読む 8月23日
藤原和博氏の著書『学校がウソくさい』は、現代の教育の姿を鋭く切り取った一冊です。今の子どもたちは、学校だけでなく、塾やYouTube動画、漫画やゲームといった多様な場から学びを得ています。そのため、学校の存在感は教育全体のごく一部、全体の二割程度にとどまると言われます。授業時間にしても年間800時間に満たず、子どもたちの生活時間全体の13%に過ぎません。かつて「学校=学びの中心」であった時代はすでに過ぎ去ったと言えるでしょう。
学力の「フタコブラクダ化」
著者が指摘する現象の一つが、学力の「フタコブラクダ化」です。すなわち「低学力でつまずいてしまった子」と「すでに理解して先へ進んでいる子」が多数を占め、従来の授業が想定してきた「真ん中の層」が減少しているのです。この状況では、授業はあたかも観客のいない落語のように空回りし、子どもも教師も学びの実感を得にくくなります。
教員の質低下とその背景
さらに教育現場を難しくしているのが、教員の質をめぐる課題です。教員の仕事が過酷であることは広く知られるようになり、その結果として採用試験の倍率が下がり続けています。結果的に優秀な人材が集まりにくくなり、教育現場の力が徐々に削がれていく。こうした構造的な悪循環を、私たちは直視する必要があります。
オンライン授業の可能性
このような現状を踏まえ、藤原氏はオンライン授業の積極的な導入を提案します。自ら学びを進められる「勉強アスリート」のような子どもは、従来の授業に縛られず自由に学びを深めればよい。一方で、学習に困難を抱える子どもには、質の高いオンライン教材を取り入れ、教師のサポートと組み合わせることで学習効果を高められる。こうした「ハイブリッド授業」が、これからの学校に求められる形なのです。
学校の新しい定義
著者は学校を「自律して学び続けられるように、集団の力でよい学習習慣と生活習慣をつける装置」と定義します。ここでの焦点は、単に知識を与える場ではなく、「学習と生活の習慣」を身につけさせる場にあるのです。「早く、ちゃんと、いい子に」という日本社会の特徴は、学校教育が長年培ってきた文化的な成果とも言えるでしょう。
授業とコスト意識
公立小中学校には年間一人あたりおよそ100万円の税金が投入されています。これを授業1コマに換算すると、おおよそ1000円程度。はたして、今の授業はその価値に見合っているのか。そう問い直す視点は、今後ますます必要になっていくはずです。スマートフォンを含めた授業のDX化は避けて通れない課題でもあります。
情報処理力と情報編集力
加えて藤原氏は、これからの教育で重視すべきは「情報処理力」と「情報編集力」の両立だと述べます。小学校では9対1、中学校では7対3、高校では5対5の比率で、基礎的な知識をつける力と、それを組み合わせ新しい価値を生み出す力を育むことが求められるのです。AIが進歩しても、基礎知識を吸収する力は不可欠です。そして同時に、知識を組み合わせ、編集して活用する力こそ、これからの社会で真に必要とされる力になるのです。
おわりに
『学校がウソくさい』は、学校教育が抱える矛盾や限界を明らかにすると同時に、新しい教育の方向性を示しています。学校を「習慣を育む場」として再定義し、オンラインを含めた多様な学びの形を組み合わせていく。その変革をどう受け止めるのかは、大人である私たちに委ねられています。子どもたちの未来を切り拓くために、学校のあり方を真剣に考え直す時期が来ているのです。

「実力も運のうち」から考える、私たちの価値観のゆくえ 8月10日
マイケル・サンデルは『実力も運のうち』で、現代社会を支える「メリトクラシー(能力主義)」の影の部分を鋭く指摘します。努力や才能によって地位や富を得ることは一見、公平で魅力的な制度に思えます。貴族制のように生まれつきの身分で人生が決まるよりも、ずっとましではないか──多くの人がそう考えるでしょう。
しかし、サンデルは問いかけます。本当にそうか?能力や努力で成功した人は、「自分の成果はすべて自分の力のおかげだ」と思い込みがちです。すると、その成功を支えた教育環境や人との出会い、健康、時代背景など「自分ではどうにもできない運の要素」を見えなくしてしまう。そして、成功できなかった人に対して「努力が足りないからだ」と見下す傲慢さが生まれます。
この傲慢さをどう防ぐか。ひとつは「運を意識的に思い出す習慣」を持つことです。自分の人生を振り返り、「偶然の出会いや支援がなければ今の自分はなかった」と認める。もうひとつは、評価基準を一つに絞らないことです。学歴や収入だけでなく、地域や家族、芸術やボランティアなど、多様な価値を社会全体で認めることが、優越感の独占を防ぎます。
この「価値の多様化」は、AI時代においてさらに重要性を増します。近年の生成AIの進化は、これまで高度な専門知識を必要としていたホワイトカラーの業務にも急速に入り込んでいます。法律文書の作成、会計処理、プログラムのコード生成、さらには学術論文の下書きまで──AIは驚くほどの速度と精度でこなします。こうした変化は、知的労働の価値構造を根本から揺さぶります。
一方で、介護、保育、看護、清掃、物流、農業といった「エッセンシャルワーク」は、機械化や遠隔化が難しく、人間の身体性や感情の機微が不可欠です。認知症の方と手をつなぎながら散歩をする。泣いている子どもをあやす。患者の不安を察して声をかける──こうした行為は、AIの処理能力よりも人間の共感力と存在感に価値があります。
将来、社会がこれらの仕事を経済的にも社会的にもより高く評価するようになれば、それは望ましい転換です。たとえば、介護職が現在の2倍の賃金を得られ、職業として誇りを持てる環境が整えば、高齢化社会の持続可能性は高まります。また、子育てや地域活動といった「市場に乗らない価値」も再評価されるでしょう。AIがホワイトカラーの一部業務を肩代わりすることで、人間がケアやコミュニティ形成に時間とエネルギーを注げるようになる──これは文明の進化の一つの形です。
ただし、価値観が変わっても、人間は何らかの基準で優劣をつけ、差別を生み出すのかもしれません。かつては血統や性別、今は学歴や年収、将来は「AIとの協働スキル」や「人間らしさ」が新たな序列の基準になる可能性があります。サンデルの議論は、差別の根本的な構造──「誰かを下に見ることで自分の価値を確かめる」という心理──に私たちを向き合わせます。
だからこそ、必要なのは「勝者の謙虚さ」と「社会全体での価値の再分配」です。自分の成功を運と環境の産物と捉え、失敗した人に寄り添える感性。そして、一つの尺度に依存せず、誰もが何らかの場面で「尊敬される側」になれるような、多層的な価値観を育てることです。
『実力も運のうち』は、単なる政治哲学書ではなく、これからの時代を生きる私たちへの行動提案書でもあります。能力主義の魅力と限界を見つめ直し、多様な価値観が息づく社会をどう築くか──その問いは、AIが進化し続けるこれからの世界で、ますます重みを増すでしょう。

2025年7月
宗教は「心を読む脳」が生んだ? 7月13日
「神様は私の心を見ている」──。このような感覚は、宗教に特有のものに思えるかもしれませんが、実は私たちの脳の進化的性質から自然に生まれてきた可能性があります。
進化心理学者ロビン・ダンバーは、著書『宗教の起源』において、宗教は「超自然的存在への信仰」ではなく、社会的結束を高めるための進化的適応であると説きます。その背景にあるのが、「社会脳仮説」と呼ばれる考え方です。
ダンバーは、人間が安定的な関係を保てる人数の上限を「ダンバー数(約150人)」と提唱しました。集団生活を維持するためには、個々の関係性を理解し、他者の感情や意図を読み取る能力が欠かせません。
こうした「他者の心を読む力」=メンタライジングを支えているのが、脳のデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)です。DMNは、内側前頭前皮質(mPFC)、後帯状皮質(PCC)、側頭頭頂接合部(TPJ)などで構成され、自己や他者の内面を想像する時に活性化します。
ダンバーは、このDMNの働きが進化することで、人間は「見えない存在の心」──すなわち神や精霊、祖先の霊などの“心的存在”を自然に想像できるようになったと指摘します。
「神が私を見守っている」「祖先が怒っている」といった感覚は、実際には他者の心を読む時と同じ神経ネットワークが動いているのです。これは脳画像研究でも裏づけられており、対話的な祈りではDMNが活性化し、神との“心の交流”を支えていると考えられています。
一方で、仏教の瞑想や宗教的トランス状態など、「無心」や「宇宙との一体感」を感じるような体験では、DMNの活動が一時的に低下することも報告されています。このとき、人は自我の境界があいまいになり、時間や空間を超えた感覚を得ることがあります。
つまり、宗教的体験には二つのモードがあるのです。
ひとつは「神の心を読む」ためのDMN的活動、もうひとつは「自己を手放す」ためのDMNの抑制。この両方が、宗教の中に共存しています。
ダンバーは、宗教がこうした脳の機能を土台にしながら、集団内の道徳や規範を内面化させ、150人を超える大規模社会を安定させる力を持っていたと考えています。
宗教は単なる信仰ではなく、私たちの「心を読む脳」と「つながりを求める性質」が生んだ、進化の産物なのかもしれません。

2025年6月
『中動態の世界』と『責任の生成』:意志の呪縛を解く 6月28日
私たちは日々の生活の中で、「自分の意志」という言葉を当たり前のように使っています。何かを成し遂げたときには「努力した結果だ」と胸を張り、失敗すれば「自分の責任だ」と肩を落とす。しかし、本当にすべての行為は私たちの「意志」に起因するのでしょうか。国分功一郎氏の『中動態の世界』、そして国分氏と熊谷晋一郎氏による『責任の生成』は、この当たり前と思われている「意志」の概念に深く切り込み、現代社会が抱える問題に新たな光を当てています。
能動態・受動態への批判と「自己責任」の罠
現在の日本語を含む多くの言語は、能動態と受動態という二項対立の構造を持っています。この構造は、行為の主体が「する」のか、それとも行為を「される」のかを明確に区別し、行為には必ず「意志」が伴うという前提を暗黙のうちに含んでいます。この言語構造が、時に過剰な「自己責任」論へと繋がってしまっています。
たとえば、予期せぬ事故に巻き込まれた被害者が、「なぜそんな場所に行ったのか」「もっと注意していれば」と、あたかも彼ら自身の「意志」によって招かれたかのように責任を問われることがあります。実際には、様々な偶発的な要素や、本人が意識していない無数の要因が複雑に絡み合って生じた事柄であるにもかかわらず、です。このような「意志」を前提とした自己責任論は、個人の行動の背後にある複雑な状況や構造を見えなくし、苦しむ人々をさらに追い詰めることがあります。
古代ギリシャの「中動態」が示す世界
しかし、言語の歴史を遡ると、今とは異なる世界観が見えてきます。『中動態の世界』によれば、古代ギリシャ語には中動態という動態が存在していました。当時の人々は、行為が主体から外へと及ぶ場合に能動態を、行為が主体自身に返ってくる場合に中動態を用いたとされています。例えば、「自分自身を洗う」という行為は、現代語では「私は自分を洗う(能動態)」と表現されますが、古代ギリシャでは「私は洗われる(中動態)」といったように、行為が主体に作用している状態を示す動態だったのです。
この中動態の世界では、「意志」という概念はまだ明確に存在していませんでした。行為は、その行為が主体から外へと向かうのか、それとも主体自身に還ってくるのか、という「行為のあり方」によってのみ区別されていたのです。しかし、キリスト教の「自由意志」の概念が広まるにつれて、行為には必ず意志が伴うという考え方が浸透し、中動態は徐々に廃れ、受動態がその役割にとって代わっていったと国分氏は指摘します。
依存症とスピノザ:中動態がひらく自由の可能性
この中動態の概念は、現代社会が抱える様々な問題、特に依存症を理解する上で非常に有効な視点を提供します。アルコール依存症や薬物依存症に苦しむ人々に対し、「自分の意志でやめればいい」という言葉が向けられることがあります。しかし、依存症はまさに「意志ではどうにもならない」状態の典型です。彼らの行動は、自らの意志のみによって制御されているわけではなく、快楽物質の作用、環境、過去の経験など、無数の要素が複雑に絡み合って生じています。このような状況下で「意志」のみを問うことは、彼らをさらに孤立させ、回復への道を閉ざしてしまうことになりかねません。
ここで浮上するのが、17世紀の哲学者スピノザの思想です。彼は「自由意志」を否定し、人間の行動は因果律によって必然的に決定されると主張しました。これは一見すると、人間の自由を否定する思想のように思えます。しかし、国分氏は『中動態の世界』の中で、スピノザの思想を中動態の視点から読み解くことで、新たな自由の概念が見えてくると示唆しています。
スピノザは、人間はそれぞれが持つコナトゥス(自己保存への努力、自分らしさを発揮しようとする力)を発揮して生きることが大切だと説きました。コナトゥスは、まさに中動態的なあり方と深く共鳴します。それは、自らの外に何かを能動的に働きかけるというよりも、内側から湧き上がってくる衝動や生への力動に身を委ね、自らの本質を発揮していくような、主体と客体の区別があいまいな行為のあり方と言えるでしょう。
「意志」という概念から自由になることで、私たちは「コントロールできないもの」を受け入れ、多様な要素が絡み合って生じる現実をより深く理解できるようになるかもしれません。そして、依存症のような「意志の弱さ」として片付けられがちな問題に対して、より本質的なアプローチを考えるヒントを得られるはずです。
責任の再構築へ
『責任の生成』では、この中動態の議論をさらに深め、「責任」という概念を再構築しようと試みます。私たちは、行為の主体が「意志」によって行為を為したからこそ責任を負う、という現代的な責任論に縛られがちです。しかし、中動態の視点から見れば、行為は必ずしも明確な「意志」から生まれるわけではありません。
熊谷氏は、障害当事者としての経験から、体が思うように動かないことや、社会の側が用意する前提によって自身の行動が制限されることなど、決して「意志」でコントロールできない事柄が人生には多く存在すると語ります。そうした状況下で、依然として個人に「自己責任」を問い続けることは、あまりにも残酷です。
「意志」という枠組みから一度離れて行為を捉え直すことで、私たちは、行為の背後にある環境、身体、偶然性といった多様な要素に目を向けることができるようになります。そして、個人の「意志」だけを問うのではなく、社会全体でどのように責任を分かち合い、支え合っていくべきかという、より包括的な「責任の生成」の道を模索し始めることができるのではないでしょうか。
『中動態の世界』と『責任の生成』は、私たちが当たり前と考えている「意志」や「責任」の概念を根底から揺さぶり、新たな認識の扉を開いてくれます。それは、他者をより深く理解し、互いに支え合う社会を築いていくための重要な一歩となるように思います。


2025年5月
ユヴァル・ノア・ハラリの「NEXUS」 5月27日
『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』で世界的に知られる歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリ。彼はエマニュエル・トッドと並んで、過去の深い理解から未来を見通す力を持つ希有な知性だと私は感じている。そんなハラリが近著『NEXUS』で取り上げるのは、AIによって根底から揺さぶられる情報と社会の行方だ。
NEXUS(ネクサス)とは「結びつき」を意味する言葉だが、この本で焦点となるのは、人間と情報、社会とテクノロジー、そしてAIと政治の間にある結びつきの変容である。
ハラリは冒頭で、情報空間において「真実よりも虚構のほうが伝わりやすい」という厳しい現実を提示する。なぜなら、虚構は単純で、感情に訴えるよう作ることができるが、真実は複雑で、しばしば不快であり、受け入れがたいものだからだ。例えば中世ヨーロッパの魔女狩り。狂信的な宗教裁判官クラーマーが著した『魔女への鉄槌』という本が、「恐るべき虚構」として多くの人々を巻き込み、現実の惨劇を引き起こした。これは、虚構の力が歴史を動かしうることの象徴的な一例だ。
このような背景のもと、AIの登場はさらなる情報の混乱をもたらす可能性がある。ハラリが繰り返し強調するのは、AIは「意識」がなくとも「知能」と「目標達成能力」を持ち、人間を上回るスピードで意思決定し、影響を及ぼしうるという点だ。かつての技術革新とは質的に異なる変化である。
ここで重要になるのが「自己修正メカニズム(self-correcting mechanisms)」という概念だ。ハラリによれば、歴史的に見て、情報の完全な自由市場では真実が敗れる傾向がある。そのため、民主主義が機能し続けるためには以下の2点が不可欠だという。
社会の主要な問題について、公の場で自由に話し合えること。
社会秩序と制度への最低限の信頼を保つこと。
しかし、AIが介在することでこの両方が揺らぎかねない。AIが生成する情報の洪水や、アルゴリズムによる判断が透明性を欠けば、民主的な討論の基盤が崩れ、制度への信頼も損なわれる可能性がある。
私たちは「真実はいつか勝つ」という楽観的な見方も、「ポピュリズムに抗えない」という悲観論も捨てねばならない。必要なのは、強力かつ透明性のある自己修正機能を持った制度や機関である。例えば、フェイクニュースの拡散を抑えるための仕組みや、AIの判断過程に対する市民的監視といった仕組みが求められている。
また、ハラリはAIによって「民主主義と全体主義世界の間にシリコンの壁が築かれる」と警告する。AIが国家の情報収集と統治能力を劇的に強化することで、自由な社会と監視社会のギャップが拡大し、それぞれの社会構造や価値観がいっそう乖離する可能性があるというのだ。
つまり、AIによる便利さを享受する一方で、私たちはその影響を制御し、社会の中にどう「自己修正」の原理を取り込んでいくかを真剣に考えなければならない。ハラリの問いは未来に向けられているが、それは今この瞬間に私たちが考え、行動すべき課題でもある。


2025年4月
イーロン・マスク 4月11日
ウォルター・アイザックソンの『イーロン・マスク(上・下)』(文藝春秋 2023)を、私はAudibleで聴きながらじっくり25時間かけて味わった。耳から入る読書は、頭の中でその人物を立体的に浮かび上がらせてくれる。イーロン・マスクという人物が、どれほど常識外れで、どれほど突き抜けているかを、私は今回あらためて知ることになった。
マスクという男は、想像以上に「変」だ。もちろん良い意味で。奇人、変人、天才、暴君、救世主。そんな相反する言葉が次々と浮かんでくる。彼は、電気自動車のトップメーカー・テスラの創業者であり、宇宙開発の最前線にいるスペースXの司令塔。脳とコンピューターを直結させるNeuralinkの開発、AI分野でChatGPTに挑むGrokの創出、さらにはヒューマノイドロボット「オプティマス」の開発まで、ありとあらゆる未来技術に手を出している。
ここまでくると、ただの起業家ではない。もはや“人類の未来”そのものに取り憑かれているような男だ。
驚くべきは、彼の仕事ぶりだけではない。突然「悪魔モード」に切り替わり、側近たちを恐怖に陥れる。あるいは「修羅場モード」となって、自ら先頭に立ち、不眠不休で社員たちと働き続ける。旧Twitter(現X)を買収した際には、全社員の8割を一気に解雇。やることが、いちいち常軌を逸している。
だがその狂気の裏には、並外れた痛みと孤独があった。彼は自らアスペルガー症候群だと語っているが、それだけではない。父親からの虐待、家庭内の暴力。そうした過去の影が、彼の内面に深く残っているようだ。そして、父と同じように躁うつの気質を抱えている可能性もあるという。感情の振れ幅が激しく、破壊と創造の両方を同時に抱え込んでいる。
では彼は、何のために働いているのか?
私は最初、彼は莫大な富を追い求めるタイプの人間かと思っていた。しかし、この本を通してそれが誤解であると気づいた。彼は人類の未来を、本気で案じているのだ。人口減少による人類の滅亡を恐れ、11人もの子どもを持ったという話は有名だが、そこには彼なりの強い信念がある。人類を「惑星間種族」として存続させなければならない。そのためには火星移住を急がなければならない――この焦りが、彼のすべての行動を突き動かしている。
彼が若い頃に夢中になったのは、SF小説『銀河ヒッチハイク・ガイド』。それが今、現実を変えるエネルギーになっているというのも面白い。空想が現実を駆動する力になっているのだ。
マスクには、「本気でないやつとは仕事をしない」という哲学がある。本気でない部下は、容赦なく切る。その厳しさゆえに、周囲の人間は心をすり減らす。だから私は、マスクのような人が人類に必要だとは思っているが、絶対に一緒に仕事はしたくない。近くにいると消耗するに違いない。
けれど、子どもたちのことは本当に愛しているらしい。彼にとって家族もまた「人類という種の存続」の延長線上にあるのかもしれない。子どもたちを通じて、彼は自分の理想を少しでも残そうとしているのだろう。
この伝記を書いたウォルター・アイザックソンという作家もまた注目すべき存在だ。彼はアインシュタイン、スティーブ・ジョブズ、レオナルド・ダ・ヴィンチといった天才たちの評伝を書き続けてきた。そして今回はマスク。彼らに共通するのは、社会の「当たり前」を壊す力である。アイザックソンは、2年間マスクのそばに張り付き、日々の怒声も混乱も、そして天才的な閃きもすべて記録していった。だからこそ、読者はマスクの真の姿に触れることができる。
マスクという人物をどう評価すべきか。好きになれるかといえば、なかなか難しい。だが、彼のような人物がいることで、世界は変わっていく。その事実だけは疑いようがない。
マスクのように「狂気」と「天才」が隣り合わせに存在する人間をどう見るか――それは、我々がどんな未来を選びたいか、という問いでもあるのかもしれない。


2025年3月
ICT(ゲーム)との付き合い方 3月24日
先日、児童精神科医である吉川徹先生の講演を拝聴する機会がありました。テーマは「発達障害とゲーム・ネット・スマホ デジタル機器との付き合い方を考える」。また、その内容をより深く理解したいと思い、先生のご著書『ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち』(合同出版、2021年)も併せて読みました。
この講演と書籍を通じて、私が感じたことは非常に明快です。現代の子どもたちにとって、ICT(情報通信技術)の進歩は、生活に欠かせない要素となっており、その影響は避けて通ることができないという現実です。吉川先生は、ご自身が「ゲーム好き」であり、今なおゲームを楽しんでいる立場から、この問題について語られています。その誠実な姿勢が、多くの保護者や教育関係者にとって、大きな説得力を持つことは間違いありません。
「時代は後ろには戻らない」
吉川先生がまず強調されるのは、「時代は後ろには戻らない」ということです。ICTのない世界に戻ることは、もはや不可能です。子どもたちは、インターネットやゲーム、スマートフォンが当たり前に存在する社会を生きています。私たち大人がその現実をいくら批判しようと、それによって時代が巻き戻されることは決してありません。であればこそ、前に進むしかないのです。
重要なのは、この時代において「どのように付き合うか」という視点を持つことです。子どもたちがICTとどう関わり、どのように利用するのか。その具体的な「術」を、私たち大人が学び、伝えていくことが求められています。
約束は「子どもが守るもの」ではなく「大人が守らせるもの」
ここで注目したいのが、「ルールや約束は、子どもが自分の意思で守るものではなく、大人が守らせるものだ」という吉川先生の指摘です。これは、一見、当たり前のことのようでありながら、実は多くの家庭で見過ごされているポイントではないでしょうか。
特にゲームやスマートフォンの使用において、子どもが「自分でやめられない」という現実は、大人自身がよく理解しておくべきことです。大人ですら、つい「もう少しだけ」とゲームを続けたり、スマホを手放せなくなったりする経験はあるはずです。ましてや、自己コントロールの力がまだ発達途中にある子どもたちにとって、それは容易なことではありません。
そこで大切なのは、終わりやすい仕組みを大人が整えることです。たとえば、「次に遊べる時間の保証を与える」「予定通りに終わったら小さなご褒美を用意する」といった工夫が挙げられます。こうした仕掛けがあることで、子どもは安心して「終わり」に向かうことができます。
「ゲームは宿題の後」は有効なのか?
よく耳にする「ゲームは宿題の後に」というルールですが、吉川先生はこれについて再考を促しています。むしろ、「ゲームは早い時間帯に」「遊びたい気持ちが高まっている時間にサッと遊ぶ」ことで、その後の学習や睡眠に良い影響を与える場合もあると指摘されています。
夜遅い時間帯にゲームをすると、脳が興奮状態になり、睡眠の質が下がることは多くの研究でも明らかになっています。そうであれば、「ゲームは夜ではなく日中に」「遊んだ後は気持ちを切り替えて宿題に取り組む」というサイクルを作るほうが、生活リズム全体を整えやすいのです。
ゲーム本体は「保護者のもの」である
もう一つの重要な視点は、「ゲーム本体は保護者の所有物である」と明確にすることです。クリスマスや誕生日にゲーム機本体を子どもにプレゼントするのではなく、ゲームソフトのみにとどめる。あくまでゲーム機本体は親が管理し、「貸し出す」形をとることで、ルールの運用がしやすくなります。
そして、そのためには保護者自身がゲームの楽しさを理解し、実際に遊ぶことも大切です。大人がゲームを楽しむ姿を見せることで、子どもは「大人もゲームの仲間である」と感じ、対話のチャンスが生まれます。
子どもに伝えてはならない3つのこと
吉川先生は、次の3つは子どもに感じさせないよう注意すべきだと語っています。
大人はネットやゲームに興味がない、あるいは嫌っている
ネットやゲームの話題は避けるべきであり、隠さねばならない
ネットやゲームのことを大人に聞いても助けにならない
これらのメッセージは、子どもに「大人は理解者ではない」という印象を与えかねません。むしろ、大人が「安心して相談できる存在」になっていることが、ICT時代を生きる子どもたちには欠かせないのです。
「ネットとゲーム以外の世界」を体験させる
また、最も重要なことは、「ネットやゲーム以外にも、楽しいこと、やりがいのあることが世の中にはたくさん存在する」という実感を、子ども自身に持ってもらうことです。そのためには、実際の体験を重ねることが必要です。アウトドア、スポーツ、読書、ものづくり…分野は問いません。大人も一緒になって取り組み、喜びを共有することが、子どもにとってかけがえのない経験となるでしょう。
発達障害のある子どもたちにとってのICTの意味
最後に、発達障害のある子どもたち――とりわけ自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の子どもたちにとって、ゲームやネットは時に「得意分野」となりうることを忘れてはなりません。明確なルール、即時的なフィードバック、達成感といった特徴は、彼らにとって安心して力を発揮できる環境となることが多いのです。
だからこそ、ICTとの関わりを「禁止」するのではなく、「どう付き合うか」を早い段階から教えていくことが大切です。そのためには、大人自身がICTとの向き合い方を学び続ける姿勢が求められています。
大人が学ぶことで、子どもは育つ
ICTは、もはや私たちの生活に不可欠な存在となりました。その環境で子どもたちが健やかに育つためには、大人がまず学び、模範となることが何より重要です。ICT時代を生きる私たち大人が、「楽しみ方」も「ルール」も率先して示すことで、子どもたちは安心して前に進んでいけるのだと、吉川先生の言葉は教えてくれます。

2025年2月
善と悪のパラドックス 2月24日
人間はなぜ、こんなにも寛容でありながら残酷な戦争を繰り返してしまうのか。リチャード・ランガムの『善と悪のパラドックス』を手に取ったのは、「人間の家畜化」というテーマに惹かれたからです。一見、家畜化という言葉は物騒に聞こえますが、読み進めるうちに、私たち人類の歴史を問い直す大きなキーワードだと気づかされました。
ランガム氏は、私たちの攻撃性を「反応的攻撃性」と「能動的攻撃性」に分けて考察しています。反応的攻撃性は、瞬間的に起こる衝動的な暴力。一方、能動的攻撃性は、計画的で目的をもった攻撃行動だといいます。私たち人類は「自己家畜化」のプロセスによって、この反応的攻撃性をある程度抑え込むことに成功してきた。しかし能動的攻撃性は残り続け、社会性や協調性を形成するためのエネルギーにもなっている。まさに、寛容さと暴力性が同居する私たちの姿を示唆する内容でした。
興味深いのは、このプロセスをチンパンジーとボノボの比較で説明している点です。チンパンジーは極めて攻撃的で、ボノボは非常に平和的。その差は、かつての生息環境の変化が大きく関わっていたとされます。そして人間は、よりボノボに近い方向に進化してきたともいわれる。しかし決定的に違うのは、私たちが能動的攻撃性を使って「反応的攻撃性の強い個体を集団で排除してきた」という事実です。このとき、殺すという暴力を行使しながらも、社会の安定を図っていった――ここに人間の歴史の暗い側面が垣間見えるのです。
また、自己家畜化は神経堤細胞(ニューロンのもとになる細胞)の遊走の変化から説明できるという指摘も、医師として大変興味深く感じました。ベリャーエフの法則という、キツネの家畜化実験で知られる動物行動学の知見がここで登場します。生物学的な進化の観点と、人間の文化・社会が相互に影響を与え合い、私たちの行動を形成しているのだということがよくわかります。
では、なぜ戦争はなくならないのか。ランガム氏によれば、能動的攻撃性は社会性をつくるために欠かせない原動力でもあるからです。私たちは高度な協力体制を築ける一方、それを脅かす存在に対しては残忍な手を使うことを厭わない。その歴史的プロセスの延長線上に、現代の国際紛争が横たわっているのかもしれません。そして著者は、この議論が現代社会における死刑制度の正当化にはつながらない、と断言しています。いかに過去において集団が個人を抹殺することで統制を保ってきたとしても、それを今に適用する理由にはならないというわけです。
人間の深層に潜む「善と悪」を考える上で、本書はとても刺激的でした。反応的な暴力を手なずけ、能動的な協力関係を育んできた私たち人類。その光と影を見つめ直すことで、新しい「人間理解」の扉が開かれるのではないかと思います。

2025年1月
漫才論 1月24日
昨年のM-1グランプリは本当に面白かったですね。バッテリーズの「ベタ」で「アホ」な漫才は何度見ても笑ってしまいますし、真空ジェシカの独特な世界観はこれまでで最高の出来だったと思います。とはいえ、一番驚かされたのは2年連続でトップバッターとして出場し、史上初の連覇を成し遂げた令和ロマンの圧巻のステージ。特に2本目の“タイムマシン”ネタは、構成もテンポも素晴らしく、何度でも見返したくなるクオリティでした。
そんな令和ロマンのくるまが本を書いたと知り、思わず手に取ってしまったのが『漫才過剰考察』(辰巳出版 2024)です。M-1をどう盛り上げるか、時代の流れを踏まえてどんな漫才をすべきか――その“過剰”なまでの考察に圧倒されました。
特に興味深かったのは「地域による漫才の違い」についての分析。漫才発祥の地とも言える「西」(関西)は大阪弁のスピード感とツッコミのリード感が強い“しゃべくり漫才”に最適。一方の「東」(東京中心)は、標準語だとテンポはやや抑えめですが、その分ボケのインパクトが強くなるため、ボケ主導になるという視点には思わず納得しました。
さらに「南」(九州)は、ボケがやりたい放題に見えて、どこか宴会ノリの空気感がある(代表例として博多華丸・大吉)。「北」(東北・北海道・北陸)は、ボケとツッコミの仲の良さが際立つ二人の世界観(代表例としてサンドウィッチマン)とのこと。残念ながら、東海地方と私の出身である中国四国地方には“これ”といった漫才がないようで、ちょっと寂しくもありました。
もう一冊、昨年のM-1で審査員を務め、NSC講師でもあるNON STYLEの石田さんが書いた『答え合わせ』(マガジンハウス新書 2024)も読みました。漫才理論を体系的にまとめあげる姿勢はさすが「石田教授」と呼ばれるだけあります。
石田さんによれば、漫才の原点は「偶然の立ち話」。変なことを言う人に対して、常識的な立場から問いただすツッコミと観客が一体となり、いわば「被害者友の会」のような空気感が生まれると漫才は最高に楽しくなるというのです。
また、「漫才コント」と「コント漫才」の定義もわかりやすく整理されていました。
- 漫才コント:設定の中の役柄と“素”の自分を行き来する
- コント漫才:設定の中の役柄になりきって演じ切る
さらに、コントと漫才の垣根を取り払ったのがM-1で活躍した「和牛」だったという指摘には、改めて彼らの革新性を感じました。
それから印象に残ったのは、NON STYLEがネタ合わせを「本気でやらない」というエピソード。ネタを詰め込みすぎるとツッコミの井上さんが飽きてしまうため、あえて大まかな流れだけ共有するそうです。そこに石田さんがボケ方を変え続け、「いかに井上さんを飽きさせずに楽しませるか」「いかに井上さんを困らせるか」を意識しているとのこと。絶妙なバランスの上に彼らの笑いが成り立っているんですね。
私自身、漫才の構造や「なぜ面白いのか」という仕組みにとても興味があります。もし自分が漫才師だったら、徹底的に分析してネタを作り込むんだろうな、なんて想像します。しかし実際には、漫才師になりたいと思ったこともありませんし、才能があるとも思えません。でも、こうして専門家や現役の漫才師が書いた“理論書”を読むと、新しい気づきがたくさんあってワクワクしてしまいます。
くるまと石田教授、それぞれの本を読んで感じたのは、漫才の歴史と現在のスタイル、客層や舞台の違い(賞レース vs. 寄席)までを的確に分析しているところ。それぞれの考え方や視点の幅広さには本当に感銘を受けました。どちらの本も、漫才好きなら楽しめること間違いなしです。
昨年のM-1グランプリを振り返りながら、改めて漫才というエンタメの奥深さを実感した一年でした。来年、再来年と、さらに新しいスタイルやコンビが出てくるのかと思うと楽しみで仕方ありません。この二冊を読むと、きっと漫才の見え方が変わるはずです。

