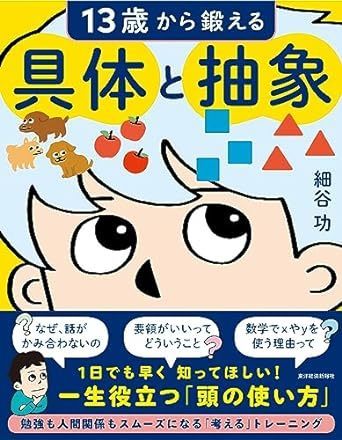2024年12月
科学的根拠で子育てを考える 12月15日
最近、中室牧子教授の新著『科学的根拠で子育て』(ダイヤモンド社)を読みました。この本は、ビッグデータを活用して子育てや教育の効果を科学的に解明し、私たちがより良い選択をするためのヒントを提供してくれるものです。何十万人、何百万人もの子どもたちのデータを基に、教育が人生に与える影響を明らかにしており、教育経済学の視点からの内容は非常に興味深いものでした。
子どもの将来にプラスとなる3つの取り組み
本書では、特に子どもの将来の収入や幸福感を向上させるために効果的とされる3つの取り組みについて解説されています。
1. スポーツ
スポーツ経験は、忍耐力、責任感、社会性を育み、自尊心を高める効果があるとされています。一部の親御さんが懸念する「スポーツに時間を使うと勉強時間が減るのでは?」という心配についても、この本は明確な答えを示しています。実際には、スポーツをすることで減るのは勉強時間ではなく、テレビやスマホといった受動的な活動時間です。
興味深い点として、スポーツの効果は女子の方が男子よりも大きいというデータもあります。また、スポーツの効果が最も顕著なのは小学生から高校生の時期であり、大学生になるとその効果については議論が分かれるようです。
2. リーダー経験
次に効果的なのがリーダー経験です。リーダーシップを発揮する機会があると、一時的に勉強時間が減ることもありますが、勉強に対する意欲や自主性が向上し、結果的に学力が高まることが多いそうです。また、リーダーシップを経験することで、社会性が磨かれ、大人になってからもプラスの影響を与えるとされています。
さらに、本書は「リーダーシップは生まれ持った才能ではなく、習得可能なスキルである」とも述べています。つまり、子どもが自信を持ってリーダーに挑戦できる環境を整えることが大切なのです。
3. 非認知能力
最後に紹介されるのが、非認知能力(忍耐力や自制心、やり抜く力など)です。例えば、忍耐力は成績だけでなく、貯蓄や健康にも良い影響を与えます。自分の感情や行動をコントロールする自制心が低い場合、健康面や経済面で不利になることが多いというデータも示されています。
特に注目すべきは、「幼少期に身につけた非認知能力は、その後の認知能力を伸ばすのに役立つが、その逆は観察されていない」という点です。このことから、幼少期の教育投資がいかに重要かを再認識させられます。
科学的根拠を活かした子育ての重要性
本書のもう一つの魅力は、個人の経験だけではなく、ビッグデータに基づく科学的な知見を提供している点です。子育てには多くの不確実性が伴いますが、このようなデータに基づくエビデンスは、親としての選択を後押ししてくれる貴重な手がかりになります。
中室教授の本には、他にも最新のエビデンスに基づいた子育てに役立つ情報が満載です。科学的な視点を持ちながら、愛情を込めて子どもと向き合うことの大切さを改めて感じました。
子育ての新しい視点や実践に役立つヒントが得られるこの本は一読の価値があります。
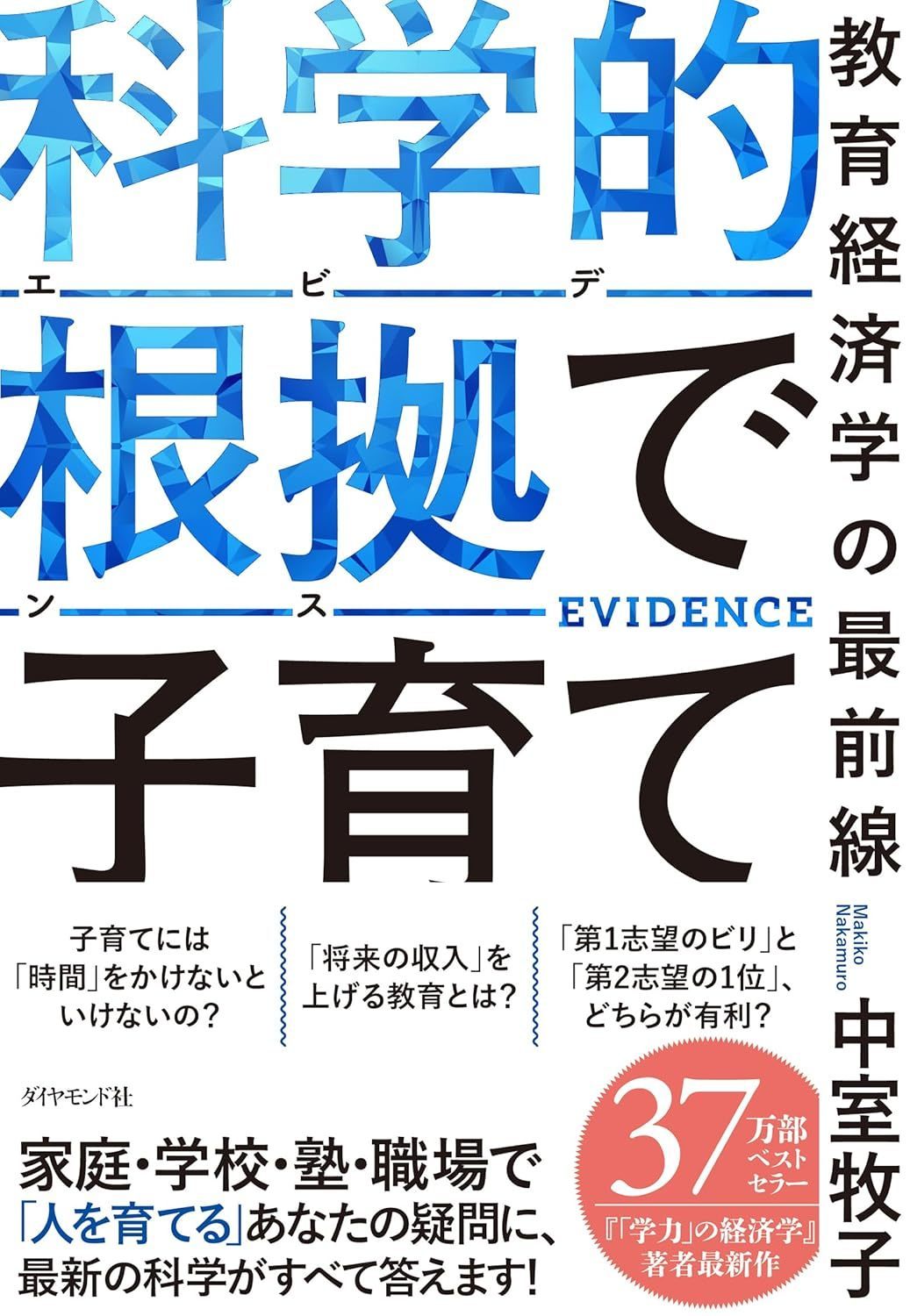
2024年11月
ネガティブ・ケイパビリティ 11月27日
精神科医で作家の帚木蓬生氏の著書『ネガティブ・ケイパビリティ』(朝日出版 2017)を読んで、現代を生きる私たちにとってこの概念がいかに重要であるかを改めて考えさせられました。ネガティブ・ケイパビリティとは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」のことです。この能力を持つ人は、性急に証明や理由を求めるのではなく、不確実さや疑問、不思議さの中に身を置き続けることができます。
この概念を最初に提唱したのは、19世紀の詩人ジョン・キーツでした。キーツはこの能力を、偉大な詩人や作家が持つ特質と位置付けています。例えば、シェイクスピアの作品には明確な善悪や解決策が描かれていない場合がありますが、その曖昧さこそが読者に深い感動と考察を促します。また、日本の古典文学である『源氏物語』を書いた紫式部も、登場人物の複雑な感情や人生の不確実性を鮮やかに描き出すことで、ネガティブ・ケイパビリティの一例を示しています。
一方で、現代社会は「ポジティブ・ケイパビリティ」を重視する傾向が強いように感じます。学校教育でも、正解が存在する問題を解くことが繰り返し求められます。その結果、不確実な状況や曖昧な課題に直面したときに耐える力を養う機会が少なくなっているのではないでしょうか。しかし、社会に出れば、正解がない、あるいは一筋縄ではいかない問題の方が多いことに気付かされます。
例えば、仕事での意思決定、人間関係の葛藤、さらには人生そのものが、簡単に答えを出せる問題ではありません。むしろ、不確実さを抱えたまま一歩ずつ進むことが求められる場面がほとんどです。その際に、性急に答えを求めるのではなく、その曖昧さを受け入れ、耐える力を持つことが重要です。ネガティブ・ケイパビリティは、単なる「耐える力」ではなく、曖昧さや不確実性を新たな可能性として捉え、次のステップへの柔軟性をもたらす力です。
現代の情報化社会では、すぐに検索すれば答えが得られる状況が当たり前になっています。しかし、これに慣れすぎると、「すぐに答えがわからない状況」に対して過剰にストレスを感じたり、無理やり解決策を作ろうとしたりする傾向が生じるかもしれません。特に、予測が難しい時代である今、不確実性に耐える力は一層重要だと感じます。
ネガティブ・ケイパビリティを磨く方法としては、詩や文学に触れることや、自分の中で答えを急がず熟成させる時間を持つことが挙げられます。日々の忙しさの中で立ち止まり、曖昧さを抱える勇気を持つことが、長期的には新たな視点や可能性を開く助けになるように思います。
私たちがこの能力を身につけることで、不確実な時代を生き抜く力を得られるだけでなく、他者の多様な考え方や価値観を受け入れる寛容さも生まれるのではないでしょうか。帚木氏の著作を通じて、この重要性を強く感じました。
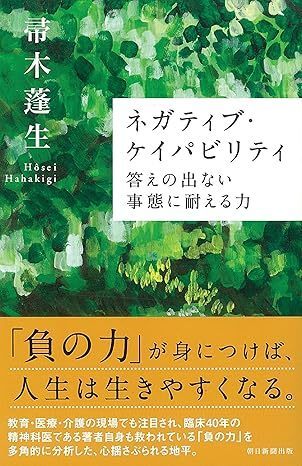
2024年10月
夢を叶えるために脳はある 10月22日
池谷裕二教授の新刊「夢を叶えるために脳はある」(講談社 2024年)は、今年読んだ本の中で間違いなく一番の一冊でした。以前から池谷教授の著作は愛読していましたが、今回の本は特に面白く、すでに2回読み返しました。これからも何度も読み返す価値があると感じています。この本は、池谷氏が脳科学を学ぶ中で培ってきた知見を、高校生への講義形式でわかりやすく伝えており、難しい内容でもスッと理解できるようになっています。
特に印象に残った内容をいくつか紹介します。
赤ちゃんの成長と脳の解釈力
赤ちゃんが成長するということは、感覚入力されたものをお手本なしに脳で解釈することだという考えが示されていました。脳が独自に「アノテーション」をしているという見方は新鮮で、学びが多かったです。記憶と時間の関係
記憶があるからこそ時間を感じることができ、過去と未来の区別ができるといいます。記憶が薄れるから過去だとわかり、逆に記憶が鮮明であると時間の流れがわからなくなるのです。実験では、記憶を増強したネズミは時間感覚が失われるという結果も紹介され、時間は実は双方向かもしれないという示唆がありました。理解と証明の本質
「エレファントな証明」という表現が印象的でした。エレガントではなく、巨大で複雑な証明を指す言葉です。人間が理解できない方法で証明することに意味があるのかという問いかけは、深く考えさせられるものでした。人工知能と人間の脳の違い
人間の脳の特徴を知るには、AIと比較することが有効だという話がありました。AIはカウンセリングや芸術においても優れている可能性が高く、無数のランダムな作品を作り出して評価を繰り返すことで進化します。一方で、人間の脳は少ない情報からすぐに思い込むことができるという特徴を持ち、それが人間らしさにつながっていると考えられます。生命の本質と宇宙のエントロピー
生命は分子の渦であり、エントロピーを急速に増大させる効果があるという考えも非常に興味深かったです。私たちが生きているだけで、宇宙の老化を助けているという視点から、脳が発達した背景には自然を効率的に破壊するためという、意外で挑発的な考えも提示されていました。
この本は、脳の不思議や人間らしさについて深く考えさせられる一冊で、ぜひ多くの人に読んでもらいたいと思います。
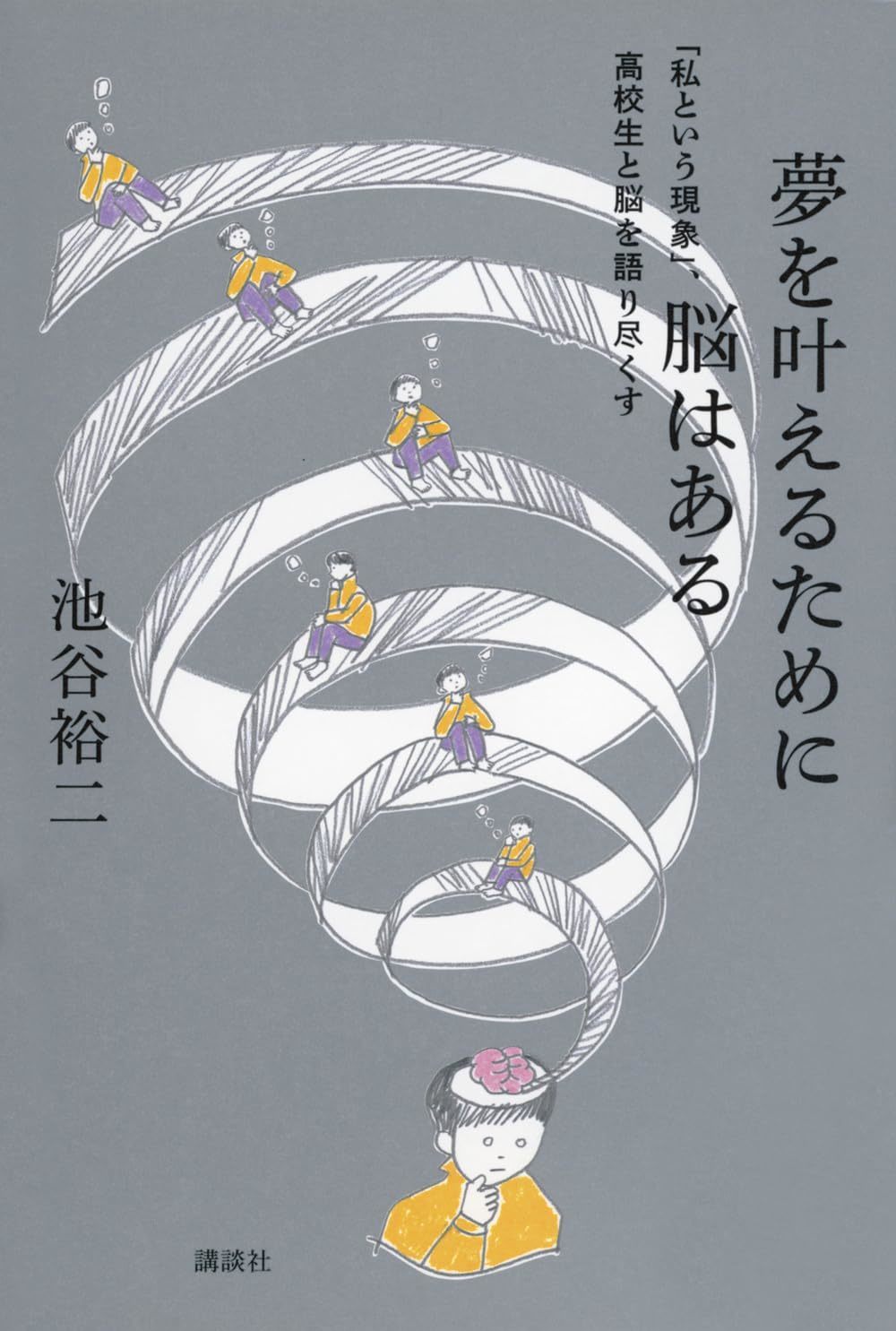
2024年9月
人間の自己家畜化 9月30日
自己家畜化という概念は、私たち人間の社会と生き方について深く考えさせられる視点を提供してくれます。精神科医の熊代亨氏の著書『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』と『人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造』を通じて、現代社会における「自己家畜化」の進行とその影響を見つめ直しました。
自己家畜化とは、生物が進化の過程で、より協調的で従順な特性を持つよう変化することを指します。例えば、イヌやネコは人間との生活に適応し、より穏やかで協力的な性質を進化させてきました。実は人間も同様に、進化の過程で自己家畜化を経験してきたというのです。これは単に生物学的な変化にとどまらず、私たちの文化や社会の中で急速に進んでいることでもあります。
生物学的な自己家畜化の一例として、ストレス反応を司るHPA(視床下部・下垂体・副腎)系の反応が低下し、またセロトニンの増加により不安や攻撃性が減少する現象が挙げられます。この生物学的変化によって、現代の人間は「かっとなって暴力を振るう」ような反応的攻撃性が低下しているのです。
この生物学的な自己家畜化の上に、さらに「文化的自己家畜化」が重なり、現代社会のあり方に強い影響を及ぼしています。文化的自己家畜化を支えているのは、社会契約や資本主義、そして個人主義です。これらの要素によって、私たちはルールを守り、合理的に未来を見据え、自己責任で人間関係を築くように求められています。このような価値観は、確かに物質的な豊かさや安定をもたらしている一方で、遺伝的に進化してきた自己家畜化と現代の文化的要請との間に乖離を生じさせています。
熊代氏は「真・家畜人」として生きることについて問いを投げかけます。文化や環境に完全に適応し、特に疑問を持たずに社会の中で安定して生きているならば、それはそれで「悪くない生き方」かもしれません。しかし、もしこの文化や環境に生きづらさを感じているのならば、さらなる文化的適応を無条件に肯定することは難しいのではないでしょうか。そして、生物学的な自己家畜化が進んだ私たちが、これからも社会の変化に追いつくことを要求され続けることに疑問を抱く人は少なくないでしょう。
現代において、特に自閉症スペクトラム(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)の診断が急増していることも、環境変化に適応できない人が増えている現状を示しています。これらの診断は、生物学的な特性に加え、社会環境にうまく適応できないという条件が含まれています。この短期間に人間の生物学的特性が劇的に変化したとは考えにくく、むしろ急速に変化する社会や文化の影響が強いと考えられます。
それでも、私たちは過去に戻りたいと思うでしょうか。確かに、昭和の時代には今よりも自由で牧歌的な部分があったかもしれませんが、その一方で、暴力やハラスメントが現在よりも蔓延していた時代でもあります。私はそのような過去に戻りたいとは思いません。むしろ、今の「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」を維持しながら、そこに生きづらさを感じる人々にとって少しでも生きやすい社会を作ることが、私たちに求められているのではないでしょうか。
熊代氏は、通年や慣習に従いながらも「心の中で舌を出していても良いはずだ」と述べています。芥川龍之介も「最も賢い処世術は、社会的因習を軽蔑しながらも矛盾しない生活を送ることだ」と記していますが、まさにこのような姿勢が、私たちが秩序に押しつぶされることなく、個々の自由を守りながら生きるために重要ではないでしょうか。
現代社会における「自己家畜化」を冷静に見つめ直すことは、私たちが今後どのように生きるべきか、何を目指すべきかを考える上で非常に大切なことです。社会の秩序を守りながらも、個人の自由や多様性を尊重し、私たち一人一人が生きやすい社会を築くために、内面で「舌を出す」余裕を持ち続けることが必要なのかもしれません。
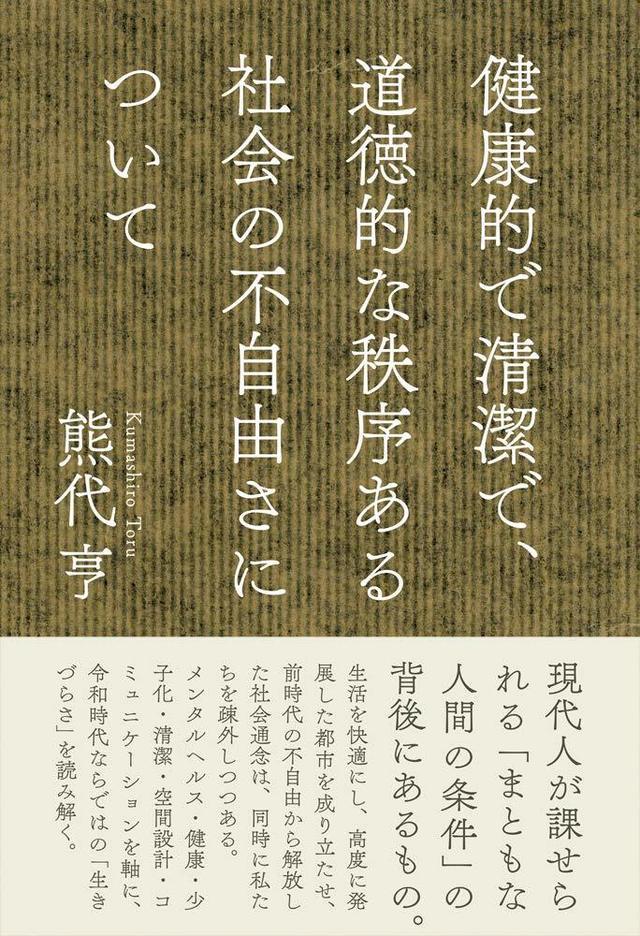
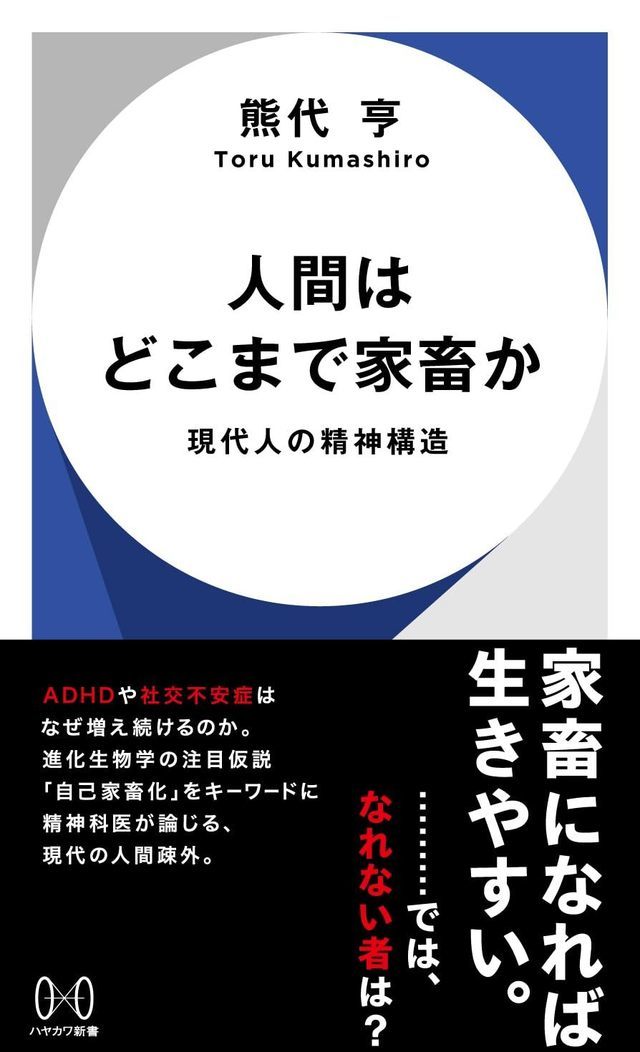
2024年8月
物理学の超入門 8月29日
YouTubeチャンネル「ReHacQ」の「ビジネスパーソンのための物理学入門」シリーズがとても面白くて、思わず夢中になってしまいました。これはカリフォルニア大学バークレー校の野村泰紀教授による講義をベースにした動画で、聞き手の高橋弘樹さんが、物理学の素人目線からたくさん質問してくれるスタイルです。物理学の魅力が野村教授の情熱とともに伝わってきて、全7本、計10時間以上の動画を一気に見てしまいました。
これらの講義を編集してまとめた本が「なぜ重力は存在するのか」(マガジンハウス 2024)というタイトルで出版されています。
実は、私は物理学が得意ではなく、学生時代もあまり勉強していなかった科目でした。でも、科学の基礎にある学問として物理学者にはとても尊敬の念を抱いていました。この動画と本のおかげで、物理学の全体像がぼんやりとですが掴めたような気がします。
特に印象に残ったポイントをいくつかご紹介します。
20世紀以降の物理学の3本柱
「相対性理論」「量子論」「統計力学」は、物理学の三大柱と言われています。驚いたことに、アインシュタインはこれら3つの分野で重要な論文を1905年のたった数ヶ月間に発表したのです。「相対性理論」だけでなく、「量子論」や「統計力学」にも多大な影響を与えていたなんて、本当にすごいです。光の速度と物体の限界
光の速度は、自然界で存在できる最高速度であり、どんな物体もこの速度を超えることはできません。理由は、速度が増すにつれて物体の慣性質量(動きを止める力)が増加し、光速に近づくと無限大になってしまうからです。つまり、光速を超えることは物理的に不可能なのです。「E=mc²」の意味
「E=mc²」はよく知られた方程式ですが、実際にその意味を考えると驚かされます。エネルギー(E)は質量(m)と光速(c)の2乗の積に等しい、つまり物質は存在するだけで膨大なエネルギーを持っているということです。たとえば、1gの物質が持つエネルギーは、広島型原子爆弾に匹敵するほどだと計算されています。この方程式がいかに重要かを改めて感じました。光子が質量を持たない理由
光子(光の粒子)が質量を持たないのは、質量を与えるヒッグス粒子と相互作用しないからです。この性質のおかげで、光は真空中で常に光速で進み、電磁気力も長距離にわたって作用することができます。時間はなぜ一方向にしか進まないのか?
時間の進行が一方向にしか進まないのは、統計的な性質によるものだと考えられます。物理学の根本的なレベルでは「時間の一方向性」は存在せず、時間という概念を使わなくても物事を説明することは理論上可能ですが、その概念を使うことで説明が簡単になる、ということなのです。
物理学者たちは、これらの事柄を数式で理解しており、物理学者を含めて私たちが具体的にイメージすることは難しいかもしれません。しかし、この動画や本を通じて、世界の仕組みが少しだけ理解できたような気がしています。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください!
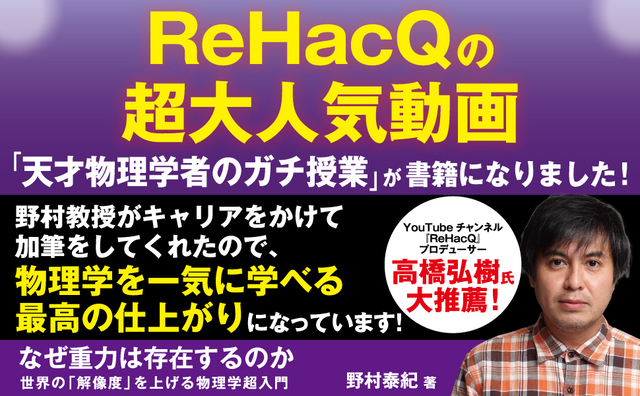

2024年7月
腸内細菌の驚くべき力 7月21日
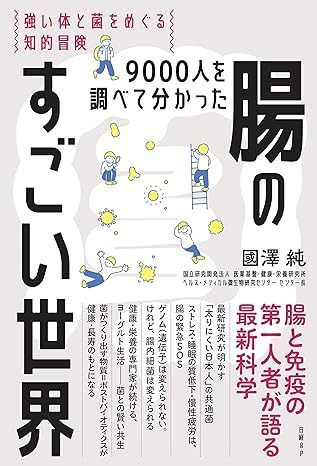
腸内細菌叢が私たちの健康や脳の働きにどれほど大きな影響を及ぼすかについて、以前から非常に興味を持っていました。多くの本や文献を読んできましたが、「腸のすごい世界 9000人を調べて分かった」(國澤純 著、日経BP、2023)は、これまでよりも一段と高いレベルのエビデンスと内容を提供してくれました。以下にその興味深いポイントをまとめてみました。
腸内細菌のリレー
腸内細菌は、食物繊維やオリゴ糖をエサにして、体にとって有益な短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸)を生成します。このプロセスには複数の菌が協力して働いています。まず、糖化菌が食物繊維を分解して糖を作り出し、その糖を材料に乳酸菌が乳酸を、ビフィズス菌が乳酸と酢酸を生み出します。さらに、別の菌がこれらの乳酸や酢酸からプロピオン酸や酪酸を生成します。
短鎖脂肪酸の主な働き
①腸内を弱酸性に保ち、有害な菌の発育を抑制し、有用菌の発育を促す。
②腸の活動エネルギーとなり、蠕動運動を促進する。
③腸管のバリア機能を強化する。
④免疫機能を整える。
⑤血糖値を一定に保つ。
⑥脂肪細胞の肥大化を抑制し、肥満を予防する。
⑦炎症を抑制し、生活習慣病の予防と改善を助ける。
炭水化物抜きダイエットの悪循環
炭水化物の摂取を減らすと、食物繊維や難消化性でんぷん、難消化性オリゴ糖も減少し、それらをエサにする菌が減少します。その結果、炭水化物から生成される短鎖脂肪酸が減少し、「太りやすく、痩せにくい」体質になってしまいます。安易な炭水化物ダイエットはお勧めできません。
老化と生活習慣病を引き起こす「腸漏れ」
腸管の上皮細胞同士の結合が緩むと、異物が体内に侵入しやすくなり、免疫細胞が異常を察知し続け、炎症が発生します。炎症が慢性化すると、異物が腸管から血液中に流れ出し、全身の臓器に炎症を引き起こし、「体の調子がなんか悪い」「だるさや微熱が続く」といった全身症状が現れます。これが静かに進行し、老化や生活習慣病を引き起こします。腸漏れの原因としては、①老化、②有害菌の増殖、③短鎖脂肪酸を生み出す有用菌のエサ不足、④腸管粘膜の減少が挙げられます。②③④については、食生活の改善で対処可能です。
まとめ
腸内細菌叢が私たちの健康に与える影響は大きいものがあります。この本を読んで知識を得て、腸内環境を整え、より健康的な生活を送ることが期待できそうです。
2024年6月
SF小説の面白さ 6月18日
ここ2か月間、数十年ぶりにSF小説の世界にどっぷりはまりました。オーディブルで計106時間、文庫本にすると7冊分を聴いていました。
まず、最初に聴いたのが「プロジェクト・ヘイル・メアリー」(アンディ・ウィアー著 早川書房 2021)でした。主人公が真っ白い奇妙な部屋で一人で目覚めるシーンから始まる。記憶は断片的で、科学的知識を駆使して現在の状況を判断し、徐々に自分の使命に気付いていく。そして、「ヘイル・メアリー号」という名の宇宙船に乗船していることが分かっていく。そこから、思いもよらないストーリーが展開されていきます。ネタバレ禁の話なのでこれ以上書くことはできませんが、ハラハラドキドキする最高に面白い話でした。ちなみに、私も知らなかったのですが「ヘイル・メアリー」という言葉は「アメリカンフットボールで負けているチームが一発逆転を狙ってゴール近くに向かって投げるパス」のことで、「やけくそ」といった意味です。
「プロジェクト・ヘイル・メアリー」でSFの面白さにはまったので、勢いに乗って中国SFの超大作「三体シリーズ」(劉慈欣 著 早川書房 2024)に挑戦しました。こちらは、「プロジェクト」をはるかに上回る81時間を要しました。スケールが大きく、空間的にも時間的にもとてつもなく広く長い物語でした。「暗黒森林理論」「光速の低速化」「曲率推進」「次元攻撃」など独特の概念が登場し、不思議な世界にさまようことができました。
私が人生で最初にSFを読んだのは中学生の時で、ジュール・ベルヌの「地底探検」「海底二万里」「月世界へ行く」などでした。子どもの冒険心をくすぐる本で、読書が好きになったきっかけの一つだったように思います。また、中学時代に一番好きだった本はジュール・ベルヌの書いた「十五少年漂流記」で、繰り返し読んだ記憶があります。
高校生になると友人にSFファンがいて「SF同好会」に入ることになりました。活動はほとんどありませんでしたが、「宇宙英雄ペリー・ローダンシリーズ」スタートしたところで、みんなで20数巻まで読んだものでした。多数のSF作家がリレー形式で書いていくシリーズで現在は700巻以上になってるようです。
大学時代はSFは全く読まなくなり、次に読み始めたのは社会人になってからでした。SFの古典的名作の「火星年代記」(レイ・ブラッドベリ)や「地球幼年期の終わり」(アーサー・C・クラーク)などを繰り返し読んだ程度でした。
数年前に岡田斗司夫氏が「これからの時代はSF小説を読むことが大事だ」と言っていたのを真に受けて、お勧めの「タイタンの妖女」「月は無慈悲な夜の女王」に挑戦しましたが、面白さを感じるところまでいかずに挫折しました。
しかし、今回「プロジェクト・ヘイル・メアリー」と「三体シリーズ」を読んでみて、SF小説の面白さを改めて見直しました。とにかくスケールが大きい。未知の世界に入った時に感じる不安と期待のような感覚を味わうことができます。物理学的な知識が随所に出てきますが、それらは気にせずに「そんなもんかな」と思ってどんどん先に進むことができます。ネタバレをしてしまうと読む楽しみを味わえなくなるので、ここに書くわけにはいきませんが、いずれの著作も私に豊かな時間を与えてくれる名作でした。
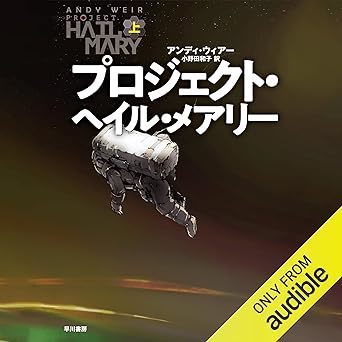
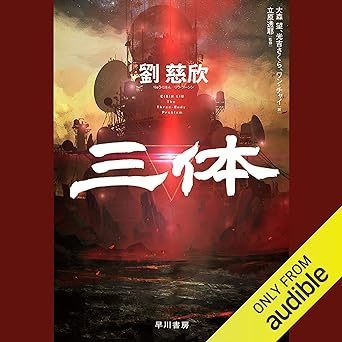
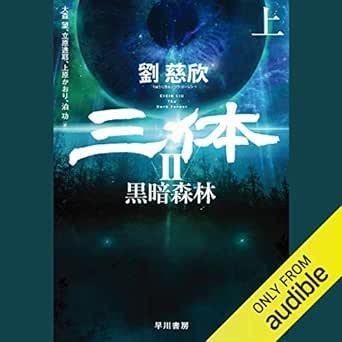
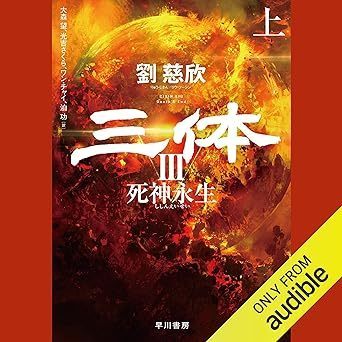
2024年5月
第39回全日本医師卓球大会 5月28日
5月26日に第39回全日本医師卓球大会に参加しました。約20年前から毎年のように参加していましたが、コロナ禍で中止を余儀なくされていました。昨年度に3年ぶりに再開された、卓球好きの医師待望の大会です。
今回は鹿児島での開催で、遠距離であることから参加を少しためらっていましたが、何かいいことがありそうな予感がして参加することにしました。最初は飛行機で行くことを考えていましたが、新幹線を利用すると5時間弱で行けることが分かり新幹線で往復することにしました。
大会は団体戦と個人戦。団体戦では5人のシングルスを年齢別のハンデ付きで戦います。参加は22チームで例年の大会と比較してやや少なくなっていました。
団体戦はまず3チームによるリーグ戦を行って、1位チームが決勝トーナメントに進出する方式です。初戦の相手は帝京大学・千葉大学の合同チーム。私はカットマンで裏に粒高ラバーを貼っているアラサーの女性との対戦でした。ハンデを少しもらっての対戦でしたが、1セット目はコテンパンにやられました。苦手の粒高ラバーの変化に対応ができなかったのです。2セット目から粒高面をなるべく使われないように作戦を変えたところうまくいき2セット目を奪取。その後流れがこちらに向いて、3-1で勝つことができました。チームも3-2で勝つことができ、勝利に貢献することができました。2戦目は鹿児島Aチームが相手。またしても、裏面に粒高ラバーを貼ったカットマンの男性。1本ハンデをもらいましたが、手も足も出ず0-3で完敗。しかし、チームは3-2で勝つことができ、愛知チームとしては久しぶりに決勝トーナメントに進出できました。
決勝トーナメント1回戦は神戸・金沢合同チーム。私の相手は西医体優勝経験のある攻撃型のシェイクハンドの男性でした。実力差はかなりあるはずでしたが、相手の人の練習不足もあるようで接戦になりました。セットカウント1-2で負けていたところで、チームの勝ちが決まり私の試合は中止になりました。しかし、これで愛知チームとしては14大会ぶりのベスト4に進出です。
準決勝は、島根・滋賀合同チームで、島根は前回大会の優勝チームです。私の相手は前回優勝メンバーの20代の私と同じ左利きの男性。シェイクハンドで裏面に粒高ラバーを貼っていました。2本ハンデをもらい私のドライブが調子がよく決まり、1セット取ることができました。しかし、明らかな実力差があることは明らかで1-3で負けました。チームとしては2勝2敗でしたが、相手チームは一人メンバーが足りなかったため、わがチームの勝ちが決まりました。
これで愛知チームとしては史上初めての決勝進出です。決勝進出の原動力は、わがチームのエース坂井先生と神がかり的な活躍を見せた森田先生で、二人ともここまで4連勝でした。私は1勝だけでしたが、私が相手チームのエース格と当たったことで間接的に勝利に貢献したと信じています。
決勝は優勝常連の大阪府医師会Aチームでした。私の相手は20代のバリバリの両面裏ラバーの男性でした。2本ハンデをもらい健闘して1セットを取ることはできましたが敗戦。チームも全敗で準優勝になりました。
私の何かいいことがありそうな予感は当たりました。実力的にはとても決勝に行けるチームではなかったのですが、くじ運の良さと神がかり的に調子のよかった先生の活躍で、愛知チームとしては大会史上初の準優勝に輝きました。
そのあとの個人戦は、2試合とも2-3で惜敗しました。団体戦でかなり疲労したことと先週の試合で痛めていた左腕の痛みが強くなったことを言い訳として挙げておきます。最後の試合が終わった時には両足がつってしばらく立ち上がれませんでした。
新幹線は快適で、本を2冊読めたのと映画を1本観ることができました。来年の全国医師卓球大会では、ぜひとも個人戦でも勝てるように練習に励みたいと思いました。減量も必要と感じました。
とても楽しい大会だったので、記録として残すことにしました。

運動の神話 5月3日
『運動の神話』(早川書房、2022年)は、ハーバード大学のダニエル・E・リーバーマン教授が執筆した一冊で、運動に関する一般的な認識に挑戦しています。このブログでは、本書が提起する運動と人類進化の関連性について、わかりやすく解説します。
リーバーマン教授は、人類が「運動をするために進化した」という考えに疑問を投げかけます。彼の研究によると、人類は運動する本能に反するように進化してきましたが、それにも関わらず、運動が健康に役立つ理由を探求しています。
地球上に現れてから約20万年が経過したホモ・サピエンスは、そのほとんどを狩猟採集社会で過ごしてきました。このため、私たちの体は1日に7時間の軽作業に適応しており、活発な活動は1時間程度だと推定されています。しかし、狩猟採集民の運動は生存のためであり、無駄なエネルギー消費を避けるために最小限に抑えられていたと指摘されています。
現代社会では、長時間座って過ごすことが多いため、定期的な運動が健康を維持するために必要です。特に、筋肉を動かさないと血中の脂肪や糖の濃度が高まり、炎症を引き起こす可能性があります。炎症を抑えるタンパク質「マイオカイン」は筋肉を動かすことで放出されるため、運動が重要であることが再確認されています。
人間の持久走能力に関する興味深い進化的背景が説明されています。特に、「肉が食べたいから」という動機から、約200万から300万年前に私たちの先祖は腐肉漁り(スキャベンジング)という行動を始めたとされています。これは、真夏の酷暑の中、ハゲワシが飛ぶ下で長時間走り続けることで、他の動物が到達できない腐肉を獲得する戦術です。また、「持久走ハンティング」の戦略が人類の進化にどのように影響を与えたかも説明しています。これは、疲れ果てるまで獲物を追い続ける狩猟方法で、高速で短距離を走る獲物を疲労させることによって捕らえる技術です。この方法は古代人が食料を確保する上で中心的な役割を果たしました。
この過程で、私たちの体は大きな臀筋、アキレス腱、長い脚、安定した頭部を支える特化した頭蓋骨の構造を備え、他の動物には見られない独特の体温調節能力を発達させました。人間は1時間に1リットルもの汗をかくことができ、これにより32℃の熱中でも体温を効率的に下げ、冷却を保つことが可能です。この能力は、人間が長距離を持続的に走ることを可能にし、「持久走に限れば、動物の中で人間が一番速い」という事実を支えています。
この本は、運動の意義や進化的な背景について、新たな視点を提供する興味深い作品です。日常生活における運動の価値を再考するきっかけとなる一冊です。
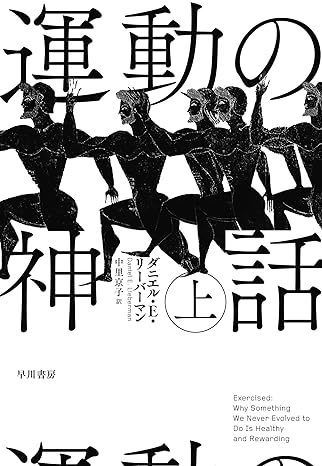
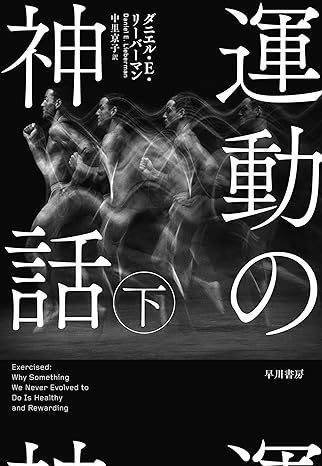
2024年4月
すばらしい人体と医学 4月8日
私は小学校の時から社会が大好きで、家に置いてあった全20巻の百科事典の社会系(地理や歴史)の10冊は何度も読んでいました。一方で理科系の事典は興味がわかず、読む気になりませんでした。機械類にも興味なく、高校に入って文科系と理科系の進路を決める時にも迷わず文科系を選択しました。物理はもちろん、化学にも生物にも興味は持てず、大学は文学部に進みました。事情があり医学部を目指すことになり、化学を受験用に勉強し何とか医学部に合格しました。入学後の教養部では理科系の科目に歯が立たずぎりぎりの成績で専門科目の始まる3年生になることができました。
しかし、生理学・病理学を学び始めると、俄然勉強が面白くなりました。「医科生理学展望」「ガイトンの生理学」および病理学の「Basic Pathology」などの教科書を読んでいると、夢中になり時間が過ぎるのも忘れました。ヒトの体の中で起きていることを学ぶことは、とても知的好奇心をくすぐられ楽しかったのです。
外科医の山本健人氏の著書「すばらしい人体」「すばらしい医学」(ダイヤモンド社 2021 2023)を読むと、改めて医学生の時に味わっていたヒトの身体を知ること、そして医学の発見の歴史を知ることの楽しみを思い出させてくれます。
興味深かったところをいくつか挙げてみます。
GLP-1受容体作動薬:最近、糖尿病治療薬としてだけでなく、やせ薬としても知られるようになったこの薬は、アメリカドクトカゲの毒から発見された成分をベースに開発されました。この事実は、自然界の生物から得られる知見がどれほど医学に貢献しているかを示しています。
放射能の発見とその誤用:キュリー夫妻とベクレルによる放射能の発見は、その時点で人体への影響が完全には理解されておらず、ラジウムを含む製品が健康に良いと宣伝された時期がありました。これらの製品の中には、歯磨き粉や夜光塗料などがあり、特に夜光塗料を塗る若い女性作業員の間で重篤な健康被害(顎の骨の障害や白血病など)が発生しました。
消毒の歴史:18世紀までヨーロッパでは、瘴気説が流行病の原因と信じられていましたが、ジョン・スノウとイグナーツ・ゼンメルヴァイスの努力が後の消毒法の発展につながりました。スノウはコレラの原因を水によるものと特定し、ゼンメルヴァイスは産褥熱の予防に手洗いの重要性を訴えましたが、当時は広く認められませんでした。リスターによる消毒法の改良が医学界で認められるまで、時間がかかりました。
麻酔法の発展と論争:麻酔法の発明に関するアメリカの論争や、その過程での歯科医のウェルズとモートンの努力と挫折は、医学の発展における個人の貢献と悲劇を浮き彫りにします。
外科手術技術の進歩:自動縫合器の発展や、手術中にガーゼを数える難しさを克服するためのディープラーニング技術の応用など、外科医ならではの話が面白かったです。
以前に読んだことのあることも多くありましたが、何度読んでも医学の素晴らしさとその歴史の深さを認識させられます。山本先生の本はお勧めです。
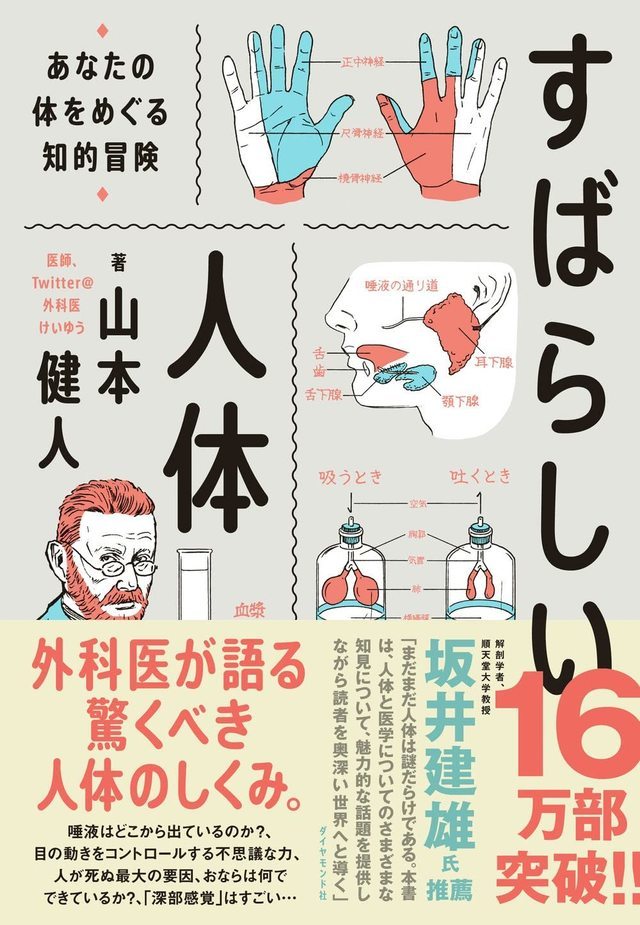
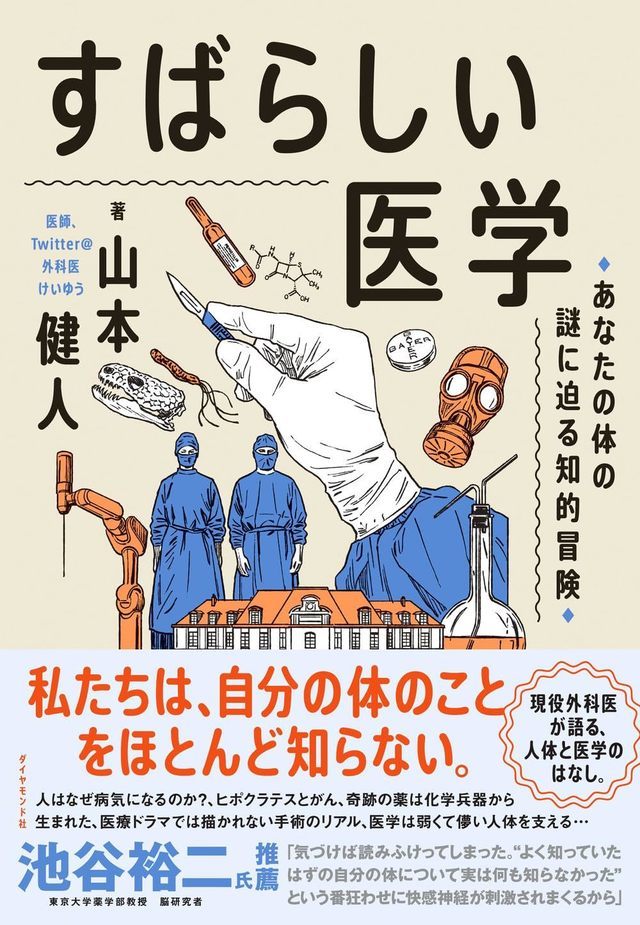
2024年3月
行動経済学的勉強の促し方 3月23日
行動経済学は、人々の意思決定プロセスにおける心理的、社会的、感情的な要因を研究する学問です。この学問は、教育や子どもの勉強習慣に対しても興味深い情報を提供してくれます。そこで、行動経済学の原理を応用して子どもたちが勉強にもっと関心を持つよう促す方法について、具体的なアプローチを「行動経済学の使い方」(大竹文雄著 岩波新書 2019)「心のゾウを動かす方法」(竹林正樹著 扶桑社 2023)などを参考にして紹介してみます。
竹林氏は人の心を象(直感)と象使い(理性)の関係で説明しています。象は力がとても強く頼もしい存在ですが、自分のことが好きで面倒くさがりで、損をするのが大嫌いという性格があり、情報を歪んで解釈する習性(認知バイアス)があります。それに対して、象使い(理性)は普段は休んできますが、象(直感)では対応が難しい重要な判断が必要な時に出てきて働きます。しかし、象使いの発動には多大なエネルギーが必要で、すぐにパワーが枯渇してしまいます。行動経済学的な考えを利用することで象使い(理性)の消費エネルギーを節約することができ、より合理的な行動をとることができるのです。
1. 目標設定と進行状況の可視化
目標設定は、モチベーションを高める上で重要な役割を果たします。子どもたちと一緒に短期的および長期的な学習目標を設定し、それらを目に見える形で表示することが有効です。進捗をトラッキングすることで、子どもたちは自分たちの成長を目で見て感じることができます。この進行状況の可視化は、小さな達成感を与え、さらなる努力へと導くことができます。
2. ナッジ理論の活用
ナッジ理論は、人々の選択をより良い方向に微妙に促すアプローチです。ナッジとは「そっと後押しする」「ひじで軽くつつく」という意味の英語です。子どもが勉強する環境を整えることは、学習へのナッジとなります。たとえば、静かで整理整頓された勉強スペースを用意する、学習に必要な資材を手の届くところに置くなど、学習行動をとりやすくする工夫があります。また、勉強時間をルーティンとして確立することも、良い習慣を形成するのに役立ちます。
3. 報酬システム
行動経済学では、即時の報酬がモチベーションを高めることが示されています。勉強することで得られる長期的な報酬(良い成績、知識の習得など)は抽象的であり、子どもたちには理解しにくいかもしれません。そこで、短期的な報酬を設けることが推奨されます。例えば、一定の勉強時間を達成したら、好きな活動(ゲームなど)を少しする時間を与えるなど、勉強と報酬を直接的に結びつけることはとても有効です。
4. 選択の自由
人は選択肢を与えられると、より頑張ることができます。子どもたちに、何を勉強するか、いつ勉強するかなど、いくつかの選択肢を提供しましょう。完全な自由を与えるのではなく、親が設定した少数の選択肢の中から選ばせることが大事で、子どもたちは自分で決定したという満足感を得られます。
5. 社会的証明と同調効果
人は他者の行動に影響を受けやすいという特性を持っています。これを社会的証明や同調効果と言います。子どもが学習に前向きになるよう促す一つの方法は、学習習慣が良い友人や兄弟姉妹、または有名人のポジティブな例を示すことです。家庭内で親が読書や自己啓発に時間を割く姿を見せることも、強力な模範となります。子どもたちは自然と、自分たちの周りの人が大切にしていることをマネしようとします。
6. 失敗からの学び
行動経済学によれば、失敗やミスから学ぶことは非常に価値があります。子どもたちに対して、間違いは学習プロセスの一部であり、失敗から学ぶことでさらに成長できると教えることが重要です。失敗を責めるのではなく、それを乗り越えることで得られる教訓に焦点を当てましょう。このアプローチは、子どもたちのレジリエンス(回復力)を高め、挑戦への恐れを減らすのに役立ちます。
7.ゲーミフィケーション
勉強をゲームのように楽しめるよう工夫することで、学習意欲を引き出すことができます。例えば、学習目標達成に応じてバッジを獲得するシステムや、友達や家族との勉強時間競争など、競争と協力の要素を取り入れることが有効です。ゲーミフィケーションは、勉強そのものを楽しい活動に変えることができます。
子どもたちが勉強に興味を持つようになるためには、行動経済学の原理を応用することで、学習環境とモチベーションを最適化することが鍵です。目標設定、ナッジ、報酬システム、選択の自由、同調効果、失敗からの学び、ゲーミフィケーションといった戦略を取り入れることで、子どもたちの学習への意欲を高めることができるでしょう。
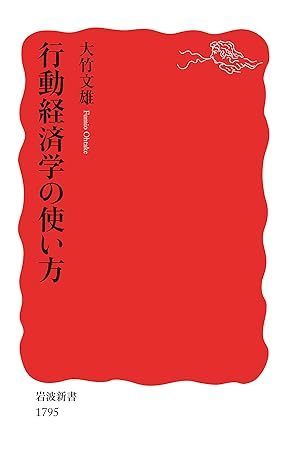
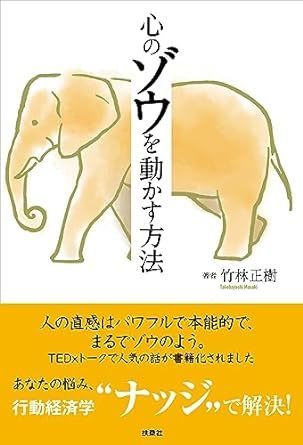
2024年2月
自己肯定感の育て方 2月15日
自己肯定感の重要性とその育て方について、スタンフォード大学オンラインハイスクールの校長である星友啓氏が著した「全米トップ校が教える自己肯定感の育て方」(朝日出版社、2022年)および「"ダメ子育て"を科学が変える!全米トップ校が親に教える57のこと」を読んで、新たな洞察を得ました。自己肯定感とは、自分自身を受け入れ、自己の価値を認識することを意味します。これは、心理学の二つの重要な概念、自己受容と自己価値に基づいています。しかし、外発的報酬に依存する自己肯定感は、短期的には効果があるかもしれませんが、長期的には心身に悪影響を及ぼすリスクがあります。
ナルシシズムのように、自分が他人よりも特別で優れていると感じ、それに応じた承認や尊敬を求めることは、健全な自己肯定感とは異なります。本当に目指すべき自己肯定感は、ネガティブな感情を認めながらも、それらと上手く付き合い、現実の自己を価値あるものとして受け入れることにあります。
ディフェンス型の心の適応力に頼りすぎず、現実を受け入れることの重要性には注意が必要です。人は複数の「顔」を持っており、例えば、職場の一員、家族の一員、趣味のグループのメンバーなどです。職場で挫折を経験したとしても、家庭内での役割や他のコミュニティで自己肯定を図ることができます。心への脅威は一つの側面に対するものであるため、他の側面を通じて自己肯定することで、心の適応を促進することが可能です。
自己肯定感を高めるための具体的な方法として、ジャーナリングが効果的です。特に、ポジティブ心理学に基づいたTGTジャーナル(Three Good Things、良かったこと三つ)は、その日に起きた良いことを3つ記録するシンプルなエクササイズです。これを時間を定めて日常的に行うことで、自己肯定感を向上させることができます。
人間の心の三大欲求である関係性、有能感、自律性を満たすことも、自己肯定感を高める上で重要な要素です。利他的な心を持ち、人に親切な行動を取ることで、自己肯定感と幸福感が同時に高まります。これは、人間の基本的な欲求を満たすからです。さらに、感謝の気持ちを持つことで、他人の目を気にせず、人間関係が改善されます。
星友啓氏の著書から得られる教訓は多岐にわたりますが、最も重要な点は、自己肯定感の育成が、単に自分を良く感じさせること以上の深い意味を持つということです。健全な自己肯定感は、心の健康、人間関係の向上、そして幸福感の全般的な向上に不可欠です。外発的な報酬ではなく、内面から湧き出る自己肯定感を育てることが、真の自己成長と幸福への鍵となるのです。
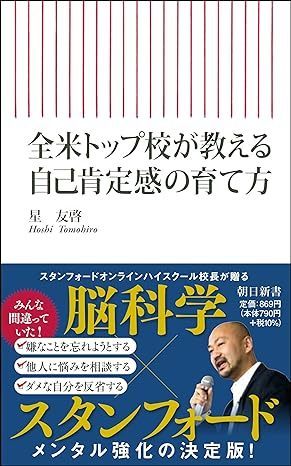

2024年1月
勉強の意義 ー具体と抽象についてー 1月14日
はじめに:勉強の意義についての考察
何故勉強するのか、これは誰もが一度は考える疑問です。私の考えでは、「勉強の意義は抽象的概念をしっかりと理解することにある」と言えます。この考え方は、細谷功氏の著書「13歳から鍛える 具体と抽象」(東洋経済新報社 2023)にも反映されており、彼の言葉が私の考えをうまく表現しています。
具体から抽象へ:教育の進行
子どもたちは学校で具体的な事実やデータから学び始めます。数学の方程式や歴史の事件など、これら具体的な知識は、広い視野で捉える抽象的な思考につながるとき、真の価値を発揮します。つまり、具体的な知識や技能が大きな概念や原則に結びつくことで、深い理解が生まれるのです。
知のピラミッド:細谷功の説明
細谷は「知のピラミッド」という概念で、知識量と抽象的思考力の関係を説明します。三角形の底辺が知識量、頂点の高さが抽象的思考力を示し、面積は知的な力を表します。このモデルは、具体的な知識と抽象的思考の重要性を視覚的に示しています。
数学の重要性:抽象的思考への架け橋
数学はその本質において非常に抽象的な学問です。概念や定理は具体的な事例を超え、普遍的な原則を示します。数学的思考は論理的推論や問題解決スキルを育成する上で不可欠であり、現実世界の問題解決においても重要な役割を果たします。
コミュニケーションにおける具体と抽象のバランス
効果的なコミュニケーションでは、具体と抽象のバランスが求められます。例えば、優れた教師は具体的な事例と抽象的概念を組み合わせて学生の理解を深めます。このバランスが、コミュニケーションをより豊かで意味のあるものに変えます。
結論:日常生活と専門的活動における具体性と抽象性
学術的な研究や専門的な領域では、具体的なデータと抽象的な理論のバランスが重要です。新たな知識や洞察はこのバランスから生まれます。日常生活や専門的な活動においても、具体性と抽象性を適切に活用することが、深い理解と効果的なコミュニケーションにつながるのです。